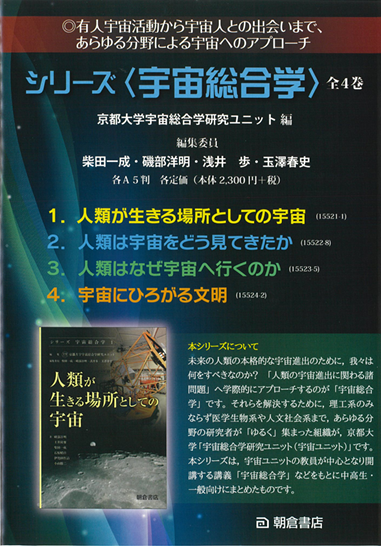コロラド大学・日本学術振興会
海外特別研究員
野津 湧太さん
京都大学理学研究科博士課程2019年3月修了、京都府立洛北高等学校出身

学部時代に同期の5人と、太陽型星での「スーパーフレア(太陽や恒星表面での巨大爆発現象)」を148個の星で365例発見し、その研究成果が、「史上初めてこの分野の統計的研究を可能にした」と評価され,共著者として科学誌「Nature」に掲載され(2012年5月)話題になった野津湧太さん。現在は日本学術振興会海外特別研究員としてアメリカ・コロラド大学ボルダー校・大気宇宙物理学研究所で「スーパーフレア」の研究を続ける。近況や、研究への思い等を寄稿してもらいました。

今、コロラドで
複数の宇宙望遠鏡及び地上の大望遠鏡での観測及びデータ解析を主に行っています。大学のあるコロラド州ボルダーは、ロッキー山脈の麓にある標高1600mの街。マラソンの高地トレーニングなどでも有名ですが、コロラド大学の他にも多数の関連研究機関があり、太陽や惑星の研究をはじめ宇宙科学分野では世界有数の研究拠点です。関連分野の研究者も多く、彼等と日々議論を交わしながら研究活動する中で共同研究の幅も広がり、アメリカに来たこと、国外へ出ることの重要性を実感しています。
太陽表面では「太陽フレア」と呼ばれる爆発現象が頻発しており、「磁気嵐」などの形で、時として地球へもその影響が及びます。京大時代から取り組んでいる研究では、この5月に、太陽表面において、通常見られるようなフレアよりはるかに巨大なフレア「スーパーフレア」が、数百年から数千年に1回の頻度で生じうることを示すことができました。この成果で、アメリカ天文学会で記者発表を行う機会をいただき、アメリカ国内外の多数のメディアで報道されるなど、大きな注目を集めました※1。
私の研究自体は観測天文学の分野ですが、もし太陽でスーパーフレアが起こったら,船外活動中の宇宙飛行士,人工衛星,電力や通信などに甚大な被害が及ぶ可能性があり、人や社会の安全にも直結するものでもあります。また7月には、太陽以外の星の周りで多数見つかっている系外惑星に対するスーパーフレアの影響を調査した論文※2が公開。生命が存在できる環境かを判定することにも結びつき、これからますます重要になっていく分野であると注目されています。
“Rare ‘superflares’ could one day threaten Earth”
https://www.colorado.edu/today/2019/06/05/superflares
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_ results/2019/190501_3.html
※2 最近の研究内容(2) 「生命が居住可能な系外惑星へのスーパーフレアの影響を算出 -ハビタブル惑星における宇宙線被ばくの定量化に成功-」
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_ results/2019/190716_1.html
学部、院生時代を振り返る
高校時代に京都大学の研究機関を実際に訪問したことがきっかけで科学に興味を持ち、入学後の選択肢の多い京都大学理学部に進学しました。
理学部では通常、研究開始は学部4回生からですが、入学してすぐに受講した『活動する宇宙』というテーマの研究室体験ゼミ(ポケットゼミ)で、花山天文台長(当時)の柴田一成先生に出会い、スーパーフレアを、惑星探査衛星ケプラーの非常に多くのデータの中から探し出すプロジェクトに誘われました。他にも理学部1回生の4名が参加。当時、スーパーフレアが見つかるとは予想されていなかったので、真剣に探す研究者はおらず、先入観がなく時間にも比較的余裕のある学部1回生に相応しいプロジェクトだったと言えます。そこで仲間とともに大きな成果を上げることができたことが、今につながっていると考えると感慨もひとしおです。
その後も柴田先生を始めとする研究者の方々や、同期の仲間から刺激を受けつつプロジェクトを進め、すばる望遠鏡などの大望遠鏡でのさらに詳細な観測などにも、学部時代から関わる機会をいただきました。研究分野が新しかったため、やればやるほど新しい成果が生まれ、それがまた研究のモチベーションに繋がり、大学院時代を経て現在に至るまでスーパーフレア研究を続けています。
高校生へのメッセージ
「宇宙の研究」と聞くと、日頃の生活とは一見かけ離れたものという印象を持つかもしれません。ただ、宇宙の起源・生命の起源といった壮大な謎を少しずつ解明していこうというような側面の他に、私の研究のように、身近な地球や社会に対する宇宙の影響を調べるというような側面もあります。また手法も、宇宙や地上の望遠鏡を使った「観測」だけではなく、新たな現象を捉えるための装置を開発する「装置開発」、観測された現象をコンピュータ・シミュレーション等も用いて追求する「理論研究」など様々です。物理や地球物理についてだけでなく、情報科学など幅広い分野の知識、知見も求められ、それらの分野の専門家とのコラボレーションも重要となりつつあります。実際、今回の成果も、非常に多数の人と議論し刺激を受け、さらには協力を得ながら進めてきた結果です。
宇宙の研究は、決して一部の優秀な人が難しい本に挑むというようなものだけではなく、面白そうなら何でも取り込んでみようというような好奇心と広い視野、多くの人とのコラボレーションが求められるものでもあります。「これには自信がある」というテーマを一つは持ちつつ、他の分野へのアンテナは常に立てておく。面白い話題があれば耳を傾け、面白い人がいれば積極的に会いに行くなどして刺激を受けてみる。そういうスタイルで取り組むと、日々の研究がとても面白いものになります。
ところで、日本国内の研究機関では、予算が年々先細りするとともに、博士課程修了後のキャリアもアメリカのような競争原理の導入によって不安定になるなど、環境はかなり厳しくなっています。私自身もこれまで、進学の節目などにそれについて考えたこともありましたし、それで悩む知人もたくさん見てきました。それでも今なお研究の道を歩んでいるのは、取り組んでいる研究が純粋に好きになれたことに加えて、一度研究者としての訓練をしっかり積んでおけば、専門分野以外の仕事に挑戦するなど、将来の可能性を広げることができるのではないかと気づいたからです。実際、周囲には、新しい分野に臆せず挑戦することで、大きな成果をあげている人は多いように思います。一つの殻に閉じこもらずに、柔軟性を持った研究者になりたいと日々心を新たにしています。