大学新入試元年を来年度に控えて
京都大学特色入試
第1回合格者による振り返り座談会
2016年度入試から始まった京都大学特色入試。
その第1回合格者のみなさんに4年間を振り返り、
これまでの生活や入学時からの変化を語っていただきました。
(本紙121号、122号に入学時の対談、座談会を掲載)
 森 詠美さん
森 詠美さん経済学部 4回生
三重県立川越高等学校出身
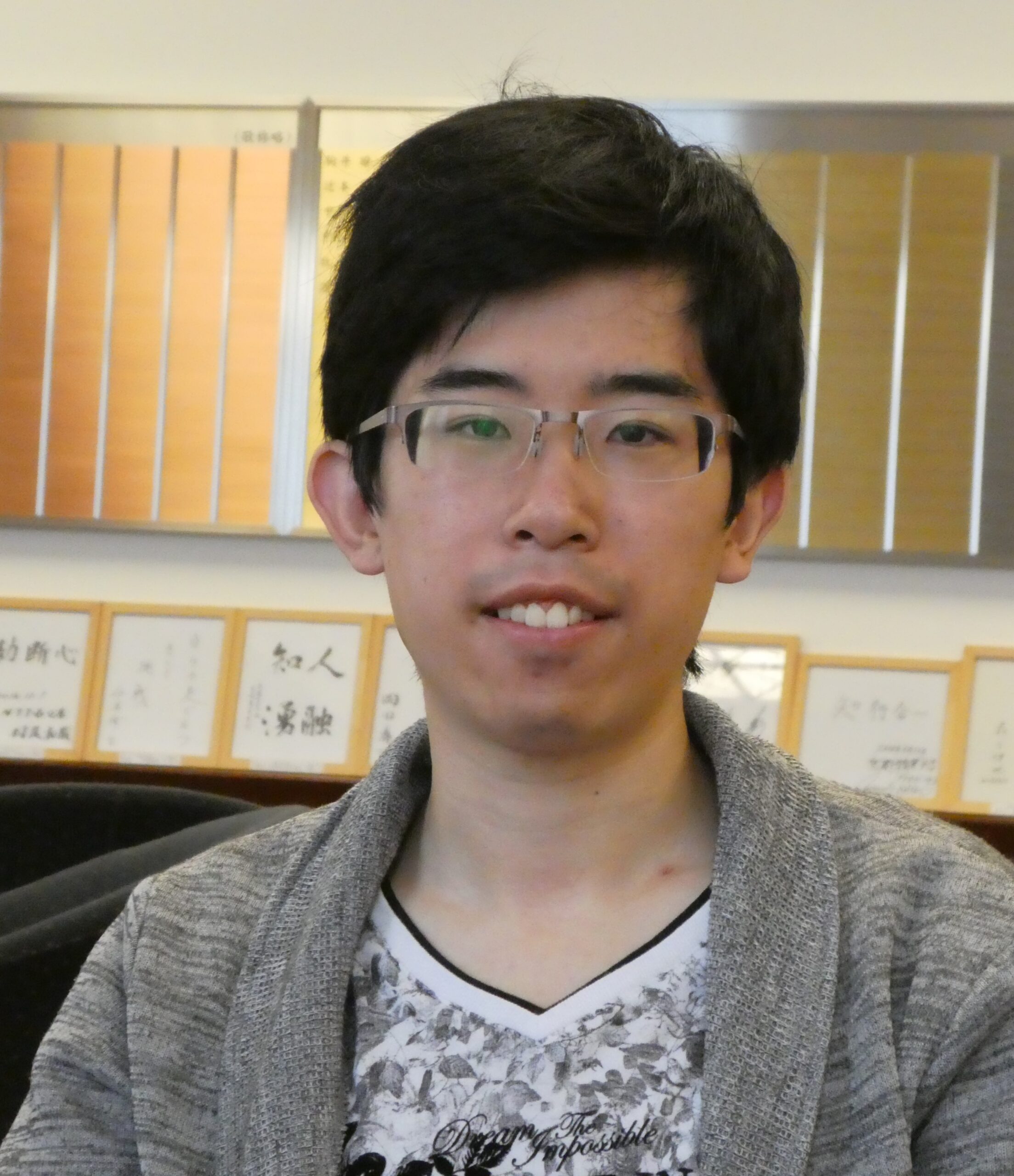 土肥 真瑳さん
土肥 真瑳さん文学部 4回生
開明高等学校出身
 若林 良輔さん
若林 良輔さん文学部 4回生
駒場東邦高等学校出身
 唐澤 和さん
唐澤 和さん教育学部 4回生
東京学芸大学附属高等学校出身
 纐纈 佳凛さん
纐纈 佳凛さん総合人間学部 4回生
滝高等学校出身
特色入試生として大学にいる中で、
他の学生との違いなどは感じましたか?
唐澤 大学から特別な追跡を受けている感じはありませんでした。他の学生と比べて何か違いがあるわけではないし、カリキュラムも差はないです。先生方に顔を覚えてもらえているなという印象はあります。教育学部の特色は5,6人しかいないので「あなた特色生だよね」と先生に言われると、ひどい点数取るわけにもいかないという気持ちになり、それはいい意味でプレッシャーでした。
纐纈 私は特色入試の合格最低点だったので、周りの特色生がしっかりやってくれるだろうと思ってあまりプレッシャーはありませんでした。特色で入れたことがラッキーって感じで、あとは自分の人生だと思い、学業もさることながらサークル活動に打ち込んでいました。私は参加できませんでしたが、最近、総合人間学部の特色生が先生に集められて話をしたと聞きました。
森 私も同じように他の人と比べて何も変わったことはありませんでした。経済学部は25人ほど特色生がいましたので特別扱いということもありません。経済学部ということもあって、経営系ゼミに入って、周りの人が経営学をきっちり勉強する中で美術を軸に持った自分がいるのは特色で入れたからかなと思いますね。変なヒトがいると思って面白がってもらえたので、居づらさはなかったですね。 若林 自分の研究室の教授に「僕は特色で入ったんですよ」と話をしたら「そうなの?」と言われました(笑)。特色だから先生方に見られているかもと思ってましたが、先生たちでも知っている人と知らない人がいるんでしょうね。
特色生であることで何か困った点は?
纐纈 合格が決まるのが一般入試生よりも一月ほど早いので、受験勉強していた時に比べて入学時は少し英語力が落ちたかなと思う部分がありました。最後の最後に根詰めて勉強することもありませんでしたから。周りの友達が頑張っていたので一緒に頑張れた部分もありますが、モチベーションを保って勉強し続けるのが少し難しかったですね。
若林 そうですね、大学始まるまで何をモチベーションにしたらいいのかわからなかった。合格決まってから勉強しなかったな…(笑)。
土肥 早めに合格が決まったことで新生活に向けてゆっくり準備できたのはよかったですね。
森 数学が得意ではなくて、特色入試では数学を解くことなく入学したので当初は不安もありましたが、大学なので数学があまり必要でない授業を選択できますし、数学が必要になったとしてもできる人に助けてもらえたので、特段困ったことはありませんでした。 唐澤 一般入試を通っていないという多少の後ろめたさはありました。私たちの年から始まった特色入試だから、ついていけなかったら特色入試を自分が否定する例になってしまうので。やや強迫観念的でもありましたけど、おかげでやる気を維持できました。結果的には良かったですね。
みなさんは入試の際に4年間の学習計画を
記した「学びの設計書」(以下、設計書)を
大学に提出していますが、
そこで書いたこととの相違点や、
書いたことで学生生活への影響は
ありますか?
森 私は現代アートのマネジメントに取り組みたくて、美術史などを扱う文学部ではなく経済学部に入りました。そこから自分のやりたいことがぶれることはありませんでしたね。経済学部での学びはアートに特化していたわけではありませんが、授業を通して経営学に興味を持てて自分の幅が広がったと思います。アート関連のスキルは、展覧会の企画運営にバイトやインターンを通じて携わることで勉強していました。春から就職することは決めているのですが、自分がどういう形でアートに携わるのかを少し悩んでいます。キュレーター(※博物館や美術館で研究・展示・保存・管理などを行う役の人)になりたいのですが、展覧会の企画運営に徹するのか、その内容に対して責任を持つ立場につくのか、というところでまだ決めかねています。
若林 卒論で扱う内容もこの先の大学院でやろうと思っていることも、設計書の通り地方交通についての研究です。高校生のときと違うことと言えば、もう少し現実に即した考え方をできるようになったことでしょうか。地方都市には新しいことに取り組むお金も体力もないことや、海外と日本では公共交通に対しての感覚が違うので、海外のシステムをそのまま日本に取り込むのは難しいこと。実は工学部でも都市交通を扱っている研究室があること、そもそも地理学とはどういう学問で工学部とは何が違うのかなどなど、多くの視点から考えられるようになりました。その上で自分のできること、やりたいことは何か考えると、設計書に書いたことに現実味を加えたものになっていました。知識や考え方が進歩しても自分の行き着く先は同じだったんですね。
唐澤 私は教育格差に興味がある旨を設計書に書いたのですが、今取り組んでいる題材は受験に関する教育社会学で、当時の問題意識をもっと自分自身に惹きつけた形になっています。私は小学校受験を経験しているのですが、そういう人は社会全体で見たらごく少数。そういう自分が取り組むことで当事者性というリアリティや、自分がやる意味が見いだされる気がしています。
私は設計書のコピーを取って京都に持ってきていて、学年の節目ごとに読み返していました。どのゼミを選ぼうか、何がしたかったのかと思い悩んだときに設計書を読み返すと、高校生のときに考えていたことを通じて、どういう軌跡でここに来たのかが思い出されたんです。もちろん入学して変わったことはありますけど、高校の段階で思考を整理しておいたことは良かったと思います。やりたいことがないと漏らす同期の人を見ると、考えを自分の言葉にしておいてよかったなと思いますね。研究テーマが見つからないなどということはありませんでした。
纐纈 先に自分のやりたいことを整理できていたのはよかったですね。周囲には思っていた学びと現実が違うと思って転学部(学科)した人もいるので、この学部で自分は何ができるのかを、特色入試を受ける段階で調べていたことは大きな一歩でした。大学の授業を受けていく中で興味を惹く別のテーマに出会い、私は設計書とは違うテーマで卒論を書くことにしたのですが、それでもどうしてこの学部に入ったんだろうと思うことはなかったですね。サークル活動の受験生サポートを通じてたくさんの受験生と出会う中で、設計書を書き自分のやりたいことを整理するというのは重要だと感じています。
土肥 学びの設計書を書いておくというのは自分の考えを整理するきっかけにもなりますし、有言実行できる良さがありますね。ただ僕は設計書と今やっていることが違っていても全然いいと思います。多くの学部は一学科制で興味の振れ幅を許容できる仕組みになっているんですから、迷って考えて変えることは悪いことじゃない。
僕は卒論を、学びの設計書に書いていたとおりに西欧の歴史で書くことにしましたが、学びの設計書に書いたことを守らなくてはとの思いが強すぎて、視野が少し狭くなってしまったと思う部分もあります。もう少し幅広いジャンルに触れておけばよかったかな。自分が特色だというのは自分で言わなければ周囲の学友には知られないので、自分だけが気にしているだけだとは思うんですけどね。 若林 専攻や進路など色々と悩むことがあると思うのですが、その時に比較するための基軸として設計書が活躍してくれました。設計書を書いていたことで大学生活に余裕が生まれると思いますね。
後輩たちに特色入試を
薦められますか?
土肥 特色入試受けたいなと思うなら、気負わず受けてみるといいと思います。文学部の場合、特色だからって何も他の人とかわることはありませんから。自分の将来を考えるいい機会ですし。1回生のときは、負担もあることだし安易に薦めようと思わなかったかもしれないけど、今は薦められますね。
唐澤 設計書など書類の準備に時間がかかるかもしれないけど、リターンは大きいです。できることならみんな書けばいいのにと思うほどです(笑)。設計書を書いているときはきれい事ばかりだなと思っていましたけど、きれい事だとしても本心で興味のあること、勉強のことじゃなくてもこういう大学生活がしたいということを明確に認識しておけば、逆算して学生生活を思い描くことができると思います。例えば自分はたくさん留学したいから単位の取りやすいところに入ろうとか。誰でも自分が入れるところでいわゆるいい大学に行こうと考えるのは当たり前のことだと思いますが、合格することとは別の大学選びの理由を考えて、自分の中で言葉にしておくことは、入学した後、自分の指針になると思います。 纐纈 一回受験のチャンスが増えると思って受けてねっていうのは、入学当時と変わりませんね。いろんな問題解くのが好きだった身としては、特殊なタイプの問題を解けるのは楽しいし、一般入試とは違う見方が得られるという点ではお薦めできます。でも、今後、入試制度が変わることも踏まえると、書類準備に負担はあるので、一般入試で手いっぱいなら無理して受ける必要はないかなとも思います。
あらためて4年間を振り返って、
これからの進路についてお聞かせください。
森 今も就職に関して悩んでいますが、大学に入るときも京大かロンドンの美大kかで迷っていました。きっとロンドンの美大に行っていたとしても京都にいたらよかったと思う部分もあったと思いますし、選んだ道以外のことについては、いい悪いは言えないというのが本音です。京都にいたことで、たまたまの縁ですが展覧会の企画などに携わったりできましたし、経済学部の同期は外資のコンサルや金融機関に行く人が多いのですが、そういう人たちと一緒に勉強できたのは面白かったと思います。そういう意味では京都にいてよかったと思いますね。
纐纈 私は自分が特色生であるというプレッシャーを感じることもなく、のびのび過ごせたと思います。回生(学年)が上がるにつれて自分が特色生であることを忘れていってしまうほどでした。学生生活を振り返るとサークルに力を入れすぎてしまったかなとも思いますが、授業を通じて都市環境に興味を持ち、就職もインフラ系に進むことになりました。希望すれば会社で国際事業部に所属できるので、設計書に書いていた国際問題には、大学を出てから携われたらと思っています。
土肥 後悔ではないのですが、もっといろんな人やものに触れておけばよかったと思います。学年が上がってサークル活動も落ち着いてきたので、いろんな本をゆっくり読む時間ができたのですが、面白いものがたくさんあるものだと今更ながら実感しています。先生方の専門の話を聞く中でも、それぞれにこんな面白さがあったのかと気付かされたり、未だに多くの面白いに出会っています。みなさんが大学に入ったら、専門とは一見関係のない授業に出てみたり、隣に座った学生に話しかけてみたり、ぜひ臆せず色々な物事に触れてみてください。
若林 来春から大学院に進みますが、修士課程を終えてからは就職しようと考えています。大学生になってからは、高校のときに比べて確かに自由は増えたかもしれませんが、実は本当の自由を見落としてしまっているんじゃないかとふと思うことがありました。やらない自由を謳歌するより、やる自由を掲げることが今後の自分に繋がるように感じます。4年間で自分の視野を広く保たなくてはいけないと感じたことや、実際に地方自治に携わるには、自分の手足を動かして地域の実情を知ることが必要だということを踏まえて、今は研究職にこだわらずに進路を考えたいと思います。
そして、実は何かクリエイティブな仕事をしたいなという野心があるんです。新しい環境で何かをやっている人を見ると羨ましいなとずっと思っていて、機が熟せば自分のクリエイティビティをビジネスで試してみたい。自分はポジティブ思考なので、やろうと思ったらできる気がするんです(笑)。うまく行けば周りの人が褒めて、期待してくれて、それに応えようと自分がさらに奮闘できる。そういうサイクルでここまでやって来たことがそうした自信につながっているのかもしれません。 唐澤 高校生の時に見えていた大学よりも実際の大学はよっぽど広かった。教育学、さらにはその中の教育社会学を例にとっても、こういう研究の分野があって、そこにいる院生や先生方が想像を超える熱量で取り組んでいることに驚かされました。高校時代には見えていない世界を覗き見たような、そんな4年間でした。こんなに広い世界が広がっていることを知ることができたのは意味があることだったと思います。高校生の自分にはまだ見えていない面白いこともいっぱいあるよと言ってあげたいですね。これもきれい事かもしれませんが(笑)。ほんの少しでも知の蓄積を生み出そうとしている人がいて、そういうものに触れることができたことが、京大に入学してよかったことだと思います。大学やここで活躍している人たちは魅力的で、いずれは大学院に戻りたいとは思いつつ、大学の外の社会にも面白いものがあって,それを知って好きになれたらいいなと思い、私は就職することにしました。今もまだまだ視野は狭いですが、昔に比べたら見える世界は広がりましたし、視野が広がる楽しさを4年間を通じて知ることができましたから、これからも見える世界を広げていきたいです。







