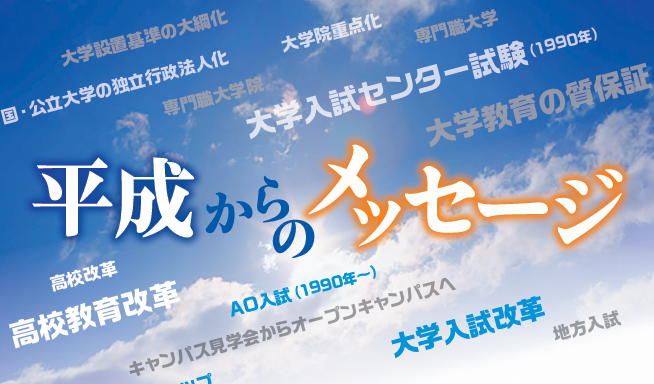
【提言】これからの進路指導を考える
「文化という総合点で大学を見直す時期が来ています」から
関西私大ジャーナル創刊号(1995年5月1日)
平成最後の大学ジャーナルをお届けします。
平成7年春、「関西私大ジャーナル」として創刊以来23年。
一面では、第一線でご活躍の大学人、識者、文化人、経済人の
お話をご紹介してまいりましたが、その中には、鋭く時代を切り取り、
未来について確かな指針を示してくれた言葉も少なくありません。
今はその謦咳に接することのできない方々のお話の中から、
次につながるコメントをご紹介します。
森 毅 先生
(1928~2010年)東京生まれ。評論家、京都大学名誉教授。東京大学理学部数学科卒。学生時代時から評論活動を開始。主な研究テーマは「関数空間の解析の位相的研究」。主著に「現代の古典解析」「位相のこころ」「数学の歴史」「異説数学者列伝」
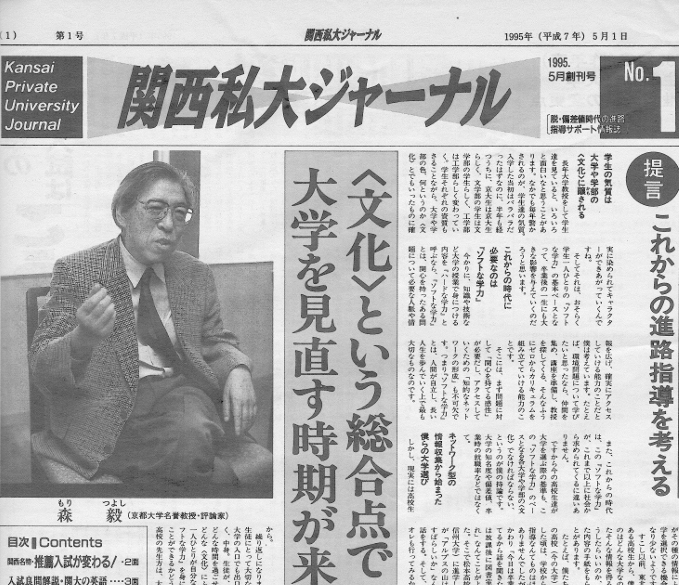
学生の気質は大学や
学部の〈文化〉に醸される
長年大学教授をして学生達を見ていると、いろいろと面白いなと思うことがあります。なかでも毎年驚かされるのが、学生達の気質。入学した当初はバラバラだったはずなのに、半年も経つうちに、京大生は京大生らしく、文学部の学生は文学部の学生らしく、工学部は工学部らしく変わっていく。学生それぞれの資質もさることながら、大学や学部の色、何というのか〈文化〉とでもいったものに確実に染められてキャラクターができあがっていくんですね。
そしてそれは、おそらく学生一人ひとりの『ソフトな学力』の基本ベースとなって、卒業後の一生にも大きな影響を与えていくのだろうと思います。
これからの時代に
必要なのは「ソフトな学力」
今かりに、知識や技術など大学の授業で身につける内容を『ハードな学力』と呼ぶなら、『ソフトな学力』とは、関心を持ったある問題については必要な人脈や情報を広げ、確実にアクセスしていける能力のことだと僕は考えています。たとえば、環境問題について学びたいと思ったなら、仲間を集め、講座を準備し、教授を探してくる。そんなふうにゼロからカリキュラムを組み立てていける能力のことです。
そこには、まず問題に対して「関心を持てる感性」が必要だし、アクセスしていくための「知的なネットワークの形成」も不可欠です。つまり「ソフトな学力」とは、人間が自立し、長い人生を歩んでいく上で最も大切なものなのです。
また、これからの時代は、この『ソフトな学力』が、これまで以上に社会から求められてくるに違いありません。 ですから今の高校生達が大学を選ぶ際の基準も、この『ソフトな学力』のベースとなる各大学や学部の〈文化〉でなければならない、というのが僕の持論です。大学の知名度や偏差値、卒業時の就職率などではなくて。
【提言】大学制度を考える
「大学は本来、独創を生み出す機関だったはずです。」から
関西私大ジャーナル5号(1996年1月1日発行)
西澤 潤一 先生
(1926~2018年)宮城県仙台市生まれ。1948年東北大学 工学部電気工学科卒。東北大学特別研究生期間満了。東北大学助手を経て、1954年助教授、1962年同電気通信研究所教授、1983年同所長、半導体研究所長も兼任静電誘導トランジスタ(SIT)をはじめ、光通信の三要素(送信源、伝送路、受信器)の発明・開発、光と電波の間の波長「テラヘルツ」の研究で知られる。1983年、日本人初のモートン賞受賞、同年文化功労者、1988年文化勲章受章。1990年~1996年東北大学総長。その後岩手県立大学、首都大学東京の学長を歴任。
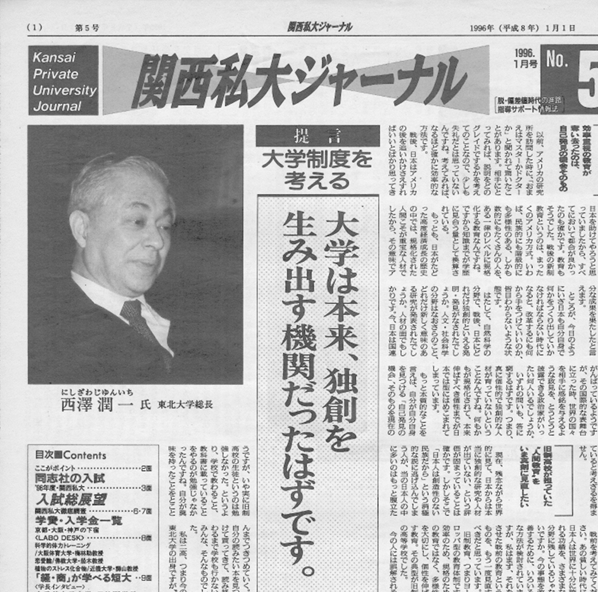
現在、残念ながら世界的に見て、日本からは本当に独創的な研究や人材が出ていない、という評価が固まっていることは確かです。しかしそこで「日本人は創造性のない民族だから」という消極的な説に逃げ込んでしまう人が、当の日本人の中に多いのはもっと腹立たしいことです。
戦前を考えてみてください。あの貧しい時代に日本人は世界に十分に誇れる功績を、さまざまな分野に残しているじゃないですか。今の事態を改善するために、いろいろな方法が検討されていますが、私はまず、それをさせた戦前の教育というものを、もう一度見直すべきだと思っています。
旧制教育、つまりヨーロッパ型の教育体制です。効率のため、規格のための教育ではなく、多様性を大切にし、個性を伸ばす教育。その典型が旧制の高等学校でした。(中略)
教育制度の複線化と
大学各自の棲み分けが
急務の課題
もちろん、大学進学率が五割を超えるような今の時代に、旧制の教育制度がそのまま有効とは考えられません。また現在のアメリカ型の教育制度にも、いい点は当然あるわけです。また社会にはヨーロッパ型の教育を受けた人とアメリカ型の教育を受けた人、両方いないといけないんですね。
そこで考えられるのが教育制度の複線化です。たとえば、四年制あるいは五年制の高校をつくる。中学と大学から一年ずつ削ってそこで一年間、徹底的な人間教育をやる。具体化するには時間がかかるでしょうが、検討してみる意義はあります。そうやって既存の学制の見直しそのものを図っていくことも重要です。
一方、大学間の「棲み分け」もはっきりさせていくことが必要です。国公立大と私立大、また国立大の中でもそれぞれの役割分担があるはずです。旧七帝大の国立大学などは、むしろ実験装置の組み立てから始めるぐらいのつもりで、基礎研究にじっくり取り組む。一方、規制の枠の外で発想も自由にできる私立大学では、当面急がれる研究や実験を、最新の設備を導入して、産学協同でどんどんやっていく。
棲み分けなんて言葉を聞くだけで、不平等だと異議をとなえる人もいるでしょうが、みんながみんな同じ方向に進まなければならないことこそ、不平等です。それぞれ違うんですから、人も大学も、それぞれの利点を伸ばしていく。それが、本当の意味での平等です。そのあたりを勘違いしたからこそ、いろいろな弊害が生まれてしまったんですね。
【提言】これからの大学を考える
「入試の弊害を憂う前に、大切なことを忘れていませんか。」から
関西私大ジャーナル5号(1996年1月1日発行)
国際日本文化研究センター所長
京都大学名誉教授
河合 隼雄 先生
(1928~2007年)兵庫県生まれ。1952年京都大学理学部数学科卒。奈良育英高等学校教諭、天理大学教授を経て1972年京都大学教育学部助教授、1975年同教授。1995年から国際日本文化研究センター所長。2002~2007年文化庁長官。

入試の多様化よりも
価値観の多様化を
大学入試の弊害がさまざまに言われています。しかし、この問題は少しぐらい制度を変えてもすぐには解決しない、なかなか難しい問題だと私は思っています。なぜなら、日本人の心の問題、すべてにからんでいるためです。
日本人というのは、大変ランク付けが好きな国民です。うちの子にはこんな長所があるんですよ、とは言わずに、うちの子は三番なんですよ、と言う。聞いている方も、それですぐに納得する。まるきり同じだと思いますね、入試制度も。一斉にテストして、一斉に点数を出して。しまいには大学にまで順番を付けてしまった。
しかも、その順番というのが、偏差値というたった一つの尺度でしかない。本来、大学にはいろんな先生がいて、生徒にだっていろんな個性がある。でも、それらはあまり評価されないんですね。順番には並べにくいから。
現在、小・中学校では「ゆとり教育」とか「個性の教育」とか、必死の教育改革が進められていると聞きます。ですが、そんな中でも、自分の子にだけは勉強させて一番に、と考えている親や教師は相当いると思います。本当に子供の将来を考えたら、それが何の得にもならないことぐらい十分わかりきっているでしょうに。
結局、日本人というのは、“個性”が何かわからないから、すべて“順番”でいこうとするんですね。この考え方を変えないかぎり、大学入試の弊害もなくならない。むしろ、日本人の心さえ変われば、入試制度なんてどうでもいいとさえ思います。
じゃあ、打つ手は何もないのかと言えば、そういうわけではないですね。
交流化と個別化が
大学の意味を変える
まず、大学について言えば、大学が変わることによって、その持っている意味を変えていくという作業が考えられます。
日本では、どこかにいったん所属したら、それで運命が決まってしまうといった考え方がかなり強くあります。今のところ大学は、その最たるものだという気がします。高校三年生の時点で決めた、あるいは決められた進学先を一生引きずっていかなければならない。それは、悲劇的なことです。
これを変えていくためには、大学間の単位互換や転部・編入の制度をもっともっと充実させて、大学間の壁をなくしていくことが必要です。それと同時に、大学ごとの特色をはっきりさせていくこと。(中略)
いつも自分を
出発点に考える訓練を
もともと私は高校の教師をしていたのですが、その頃の経験で言うと、自分なりに、「これがしたい」と決めて進学先や就職先を選んだ生徒は、三十年経った今も、やはりその人なりに満足のいく生き方をしています。さすがだと思いますよ。
自分はこれがしたい、これが好き、これが習いたい、そうやって“選ぶ力”を持っていることが高校生にとってとても大切なことなんですね。
だから、周りの大人たちは(教師だった当時は私も言いましたが)、「おまえは成績がいいから医学部へ行け」なんて簡単には言わないことです。また生徒の側も、あえて「僕にはこっちの方がいい」と言えるだけの自信を持つこと。そのためには、常に「自分が何をしたいのか」を考え続けていなければなりません。世間一般の標準とか平均とかではなしに、まず“自分”から出発する。常に、自分を生かす、自分の存在や自分の命を大切にすることを忘れないで欲しいと思います。時には、みんなと同じように勉強しなくていい、ぐらいの覚悟も必要ではないでしょうか。
しかし、考えてみれば、弊害が指摘されるほど、たくさんの人が大学に進学できるようになったことは、ものすごく歓迎すべきことです。受験戦争とは言っても、昔に比べ、特別過酷になっているわけでもありません。
さらに、ここに来て、「いい大学に入ったら幸福になれる」という、日本人の根本的な価値観そのものが、壊れかけてきているのも確かです。せっかく立派な大学に入っても、オウムに入信、なんて事件もありましたからね。
こう考えてくると私には、本当の問題は、目に見えている入試の弊害よりも、日本人が序列性に代わる新しい秩序や人間関係を、まだ見つけ出せていない、まさにその点にあるのではないかと思えるのです。今一番大切で、一番急がなければならない問題が、盲点になっている。これまでの価値観が今後も通用するはずはない。さりとて新しい秩序も人間関係も見い出せない。そうして「おもろない」と孤立している人は、みなさんの周りにもたくさんいらっしゃるはずです。
そこでもう一度、大学の話に戻るとすれば、本来、大学というのは次の時代を拓く新しい価値や秩序、そういったものを生み出す作業を担う場所でなくてはならないはずなんですね。言うなれば、世の中の根本を変革する使命を担っている。その意味で今後、大学も、そして大学に進学する人も、ますます頑張ってもらわなければならないのです。(以下略)
【提言】これからの大学教育を考える
「既成概念にとらわれない自由な発想を取り入れることが、教育改革の最大のテーマ」から
東海私大ジャーナル第2号(平成11年9月1日発行)
名古屋大学名誉教授 広島大学名誉教授
飯島 宗一 先生
(1922~2004年)長野県生まれ。1946年名古屋帝国大学医学部卒業。広島大学教授を経て広島大学学長。その後、名古屋大学医学部教授を経て名古屋大学学長。

大学の問題は
社会全体の問題
大学教育の改革ということでいろいろと言われていますが、大学のみを安易に批判することは健全とは言えません。大学教育の問題といっても大学の中だけで起こっていることのみでなく、家庭や小・中学校教育からすでに問題は始まっているのです。さらに言えばそれは効率主義や経済主義のはびこる現代社会全体の問題 だとも言えるでしょう。
企業や官僚のめざしてきた方向が現在のこの社会を作ったのだとすれば、その価値基準から一旦離れて、教育、学問が本来目指すべきものは何なのか、もっと地道に皆で議論すべきです。また、ここが悪い、あそこが悪いと、表面的な現象を非難しているだけでは解決の道は見出せません。本来めざすべきものは何かという根本問題をきちんと見据えたうえで、現実には、学問や文化を大切に、そして大学を大事にする姿勢があってこそ、良いものが生まれてくるのではないでしょうか。
東海地区の大学は
ここ十数年で格段に進歩した
東海地区は関東と関西にはさまれ、大学教育の「谷間」などと言われることがありますが、ここ十数年で事態は非常に変わってきていると思います。東海地区の各県は、進学率の面でも改善されています。今、私学が苦しいとすれば、それは東海地区に限ったことではなく、全国どこでも同じです。こんな時だからこそ、学校としてどれだけちゃんとしたことをやっているかということが問われます。
私どもはかつて、名古屋を中心にした東海地区の学長に呼びかけ、全国的にも珍しい国立、公立、私立の学長からなる「愛知学長懇談会」という集まりを結成しました。そこでは国立、公立、私立の垣根を越え、相互に学校を見学したり、問題を検討したりし、現在にいたるまでいろいろな成果を上げてきています。この大事な時期、大学教育の可能性を探るために、広い視野に立ったオープンな協力や話し合いが必要であることを強く実感します。(中略)
大学の未来は
自由な発想から生まれる
少子化によって大学の未来はどうなるかと騒がれていますが、私は全く心配しておりません。人間の文明がある限り学問自体がなくなることはありません。そのくらいでつぶれてしまう大学があるとすれば逆にそれは淘汰されていいくらいなのです。それを保護するためと称して文部省があまりに口出しをし過ぎるのは好ましくありません。そのような「護送船団方式」は自由な発想を抑えてしまい、かえって活力を失わせることになります。国はもっと大学や大学の先生を信頼するべきでしょう。
また、大学には教育の他に「学術研究」という重要なテーマがあります。日本は明治以来、先進諸国に追いつくために国として科学技術の研究に力を注いできました。その成果はけっして軽んじられるべきではありません。学問を育てる土壌には自由な発想が必要ですが、加えてそういった研究や成果を尊重する姿勢も大切です。
入試改革も
既成概念からの解放が鍵
日本の入試は「絶対平等」「機密性」「秘密厳守」を大原則にしています。そして皆、これを当然のこととして受け入れていますが、実はこういった既成概念にがんじがらめになっていることが大学入試の一番の問題です。入試の方法を小手先だけいろいろ変えてみても、そこが変わらない限り根本的には何も変わらないでしょう。たとえば私は「入試センター」だけが試験をするのではなく、いろいろな組織やエージェントがそれぞれ入試判定を行ってもよいと考えています。受けたい学生はそれを受け、その判定を採用したい大学はそれを採用すればよい。それを提案した当時は夢のようなことだと言われましたが、そういった発想を受け入れられない意識の在り方こそが、今の日本の教育の行き詰まりを招いてきたのです。「入試センター」にしろ「学習指導要領」にしろ、日本の教育は、文部省のやり方を唯一絶対のものとして受け入れる姿勢自体を見直す必要があります。そんな既成概念からどれだけ解放されるかが、「入試」だけではなく教育改革全体のテーマであり、教育の質を向上させる鍵だと私は考えています。
【提言】 これからの教育を考える
「学校は学校で、できることから始めようじゃないですか。」から
関西私大ジャーナル7号 平成8年5月1日発行
高校改革推進会議座長
兵庫教育大学名誉教授
上寺 久雄 先生
(1920~2018年)広島県出身。1960年広島大学大学院博士課程修了。小・中学校、高等学校教諭を経て、大阪教育大学教授、筑波大学教員大学院創設準備副室長、兵庫教育大学学長。その後、岐阜教育大学(現岐阜聖徳学園大学)学長。高校改革推進会議座長。
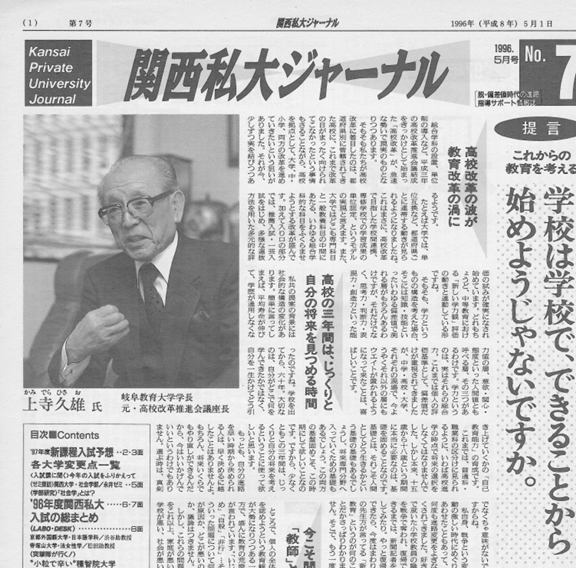
高校改革の波が
教育改革の渦に
総合学科の設置、単位制の導入など、平成三年の高校改革推進会議結成をきっかけとして始まった「高校改革」が、急速な勢いで現実のものとなりつつあります。
そもそも私たちが高校改革に着目したのは、都道府県別に管轄されてきた高校に、これまで改革の目がまったく向けられてこなかったという事情もさることながら、高校を拠点として、大学、中・小学、両方の改革を進めていきたいという狙いがありました。それが今、少しずつ実を結びつつあるようです。
たとえば大学では、単位互換など、都道府県ごとに連帯する動きが見られるようになりましたね。これはまさに、高校改革で目指した学校間連携。専修学校での学習成果の単位認定、というモデルの実現と言えます。また、大学ではどこでも専門科目と一般教養科目の中間にあたる、いわゆる総合的な科目をふくらませようとする改革が盛んです。加えて入り口の部分では、推薦入試・一芸入試をはじめ、多様な選抜方法を用いた多元的な評価の試みが確実になされ始めています。どれもちょうど、中等教育における「新しい学力観」評価の動きと連動している形ですね。
そもそも、学力というものの構造を考えた場合、そこには知識・技能といったいわゆる偏差値で測れる層がもちろんあるわけですが、それだけでなく、思考力・判断力・表現力・創造力といった能力値の層、意欲・関心・態度といった人間値とも呼べる層、その三つがあるわけです。学力というのは、実はそれらの総合力。これまでは個人の評価基準として、偏差値だけが重視されてきましたが、中学・高校・大学、それぞれの現場で、今ようやくそれ以外の層にもウエイトが置かれるようになって来たことは、喜ばしいことです。
高校の三年間は、じっくりと
自分の将来を見つめる時間
私共の提案の背景には社会的な構造の変化があります。簡単に言ってしまえば、平均寿命が伸びて、学歴が通用しなくなったのですね。学校を出てから、六十年。大切なのは、自分がどこで何を学んできたかではなく、自分を一生かけてどう引き上げていくかの「自己教育能力」の育成です。
これまでは、普通科・職業科の区分けに見られるように、いわば高校進学の時点で将来の選択をしなくてはなりませんでした。しかし本来、十五歳から十八歳という期間に本当に必要なのは、基礎を固めることなのです。基礎とは、それこそ人間としてどう生きるかという基礎の基礎もあるでしょうし、将来専門分野へ入っていくための基礎もあるでしょう。この両方の基礎固めこそ、この時期にして欲しいことなのです。ですから、少なくともこの三年間は、じっくりと自分の将来を考えるということに使って欲しいと思います。
もっとも、自分の進路を早い時期から決められる人は、早く決めるに越したことはありませんよ。もちろん、将来いくらでもやり直しができるんだから、今はいい加減でいいというわけでもありません。選ぶ時は、真剣でなくちゃ意味がないですからね。(以下略)







