集中講義
高校生の経営学
経営学部の受験を迷っている人に
洞口治夫
(法政大学経営学部教授)
小池祐二
(法政大学第二中・高等学校教諭)編著
文眞堂、2018年11月30日発行
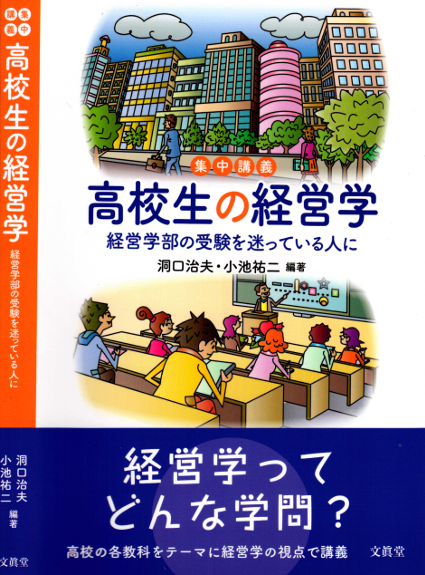
「本書は、経営学に興味を持ち、経営学部に進学しようかどうか迷っている高校生を念頭に置いて、経営学とはどのような学問なのか、経営学部ではどのようなことを学ぶのかについて紹介したもの」(あとがき)で、高校の進路指導、高校生の進路選択を悩ませてきた「経済と経営はどう違うか」、「経営学部と商学部とはどう違うか」などの《難問》解決を目指している。大学受験を控えた高校生であれば、「何のために今学んでいるのか」という疑問に突き当たるであろう。本書は、高校で学ぶ日頃の授業の意味について繰り返される素朴な疑問にたいして、「今、高校で学んでいる教科が、大学の経営学部の授業や職業選択にどのようにつながり、役立つか」を解説することで明快に答えている。
本書は、夏休みや春休み、ゴールデンウィークなどを利用した5日間の集中講義を想定した構成になっている。初日と5日目がホームルームと特別講義からなるガイダンス、その間の3日間で、体育、政治経済①②③、数学①②、英語①②、国語①②③、地理①②、世界史、日本史といった高校の教科と経営学のつながりが解きほぐされていく。統計の基礎である数学や、産業史を扱う歴史、地域の産業やまちおこしに関連する地理だけでなく、英語ではスティーブジョブズの演説やドラッガーの原文の一部が紹介され、古典では井原西鶴や『今昔物語』も「高校の教科からみた経営学」との関連で語られていく。どのような教科でも、体育までもが、経営学とは無縁ではなく、経営学が社会の広範な領域をカバーしていることが明らかになっていく。
本書に説得力があるのは、大学で経営学を教える教員と高校教員との共同作業、大学と付属高校との長年の教育連携、つまり高大連携授業の実践から生まれてきたものだからだ。本書のオリジナリティーもここにある。
同時にこのことで、本書は企画意図に反して、経営学部以外への進学を考えている生徒にも、きわめて読み応えのある一冊になっている。進路指導にあたる高校教諭にとっても、信頼のおける参考書の一冊であろう。
加えて本書には、「高校で学ぶ日本史・世界史・政治経済といった科目には、企業経営や起業家、あるいは経営学についての解説が少ない」こと、「高校の教科教育に企業経営についての丁寧な解説を加えたいという強い思いが」込められている(まえがき)。実社会や経済活動との関連を強く意識し、それが講義の随所にちりばめられているため、誰も無関心ではいられないのだ。
本書のなかの教科概説である政治経済では、「社会の課題解決に挑む企業」として、ユニークな企業やベンチャー企業が実際の取材を通して取りあげられている。食品ロスをなくそうと、スクラッチベーカリー手法で100円パンを提供するアクアベーカリー、多品種少量生産とベンチャー支援事業で著名な東京の街工場、浜野製作所等々だ。どれも現下の日本の課題を浮き彫りとするような事例となっている。高校生という多感な読者の知的好奇心や挑戦する気持ちを刺激し、将来の生き方にも強いインパクトを与えてくれるだろう。まさに筆者の言う「未来のガイドブック」となっている。
本書の構成に沿って、「1週間程度の時間をかけて、本書を読みながら、仲間と共に自分たちの未来についてディスカッション」するのもよし、もちろん一人で、空いた時間に、関心のある教科や事例、テーマから読み始めるのもいいだろう。
その結果、高校時代の学びが楽しくなり、同時に早く大学へ進みたいと思うようになるかもしれない。「なぜこんな勉強をしなければならないのか」と悩む高校生にこそ、ぜひ手に取って欲しい一冊だ。







