昨年度で三回目となった京都大学の特色入試ですが、年々受験者は増加し、試験内容にも変化が起こっているようです。今回は、そんな狭き門を潜り抜けた4名の合格者たちに話を聞いてみました。
 佐藤 源気さん
佐藤 源気さん農学部応用生物科学科
滋賀県膳所高校出身
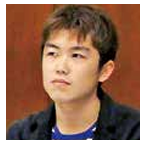 西田 恵一郎さん
西田 恵一郎さん総合人間学部(理)
奈良県奈良高校出身
特色入試を受けようと思ったきっかけは何ですか?
佐藤くん 高2の頃から生物学オリンピックに挑戦するようになり、のめり込んでいきました。バイオテクノロジーに関心があり、元から京大農学部の応生に行きたいなと思っていましたが、特色入試を知り、自分がしてきたことを活かせるのではないかと思い、受験しようと思いました。
西田くん 僕は高3の秋まで特色入試の存在を知らなかったんです。他の国立大の推薦入試を友達が受けると聞いて、京大にも推薦入試ってあるのかな?と調べてみたら、「あった!」という感じで……(笑)。それで0.1%でも受かる確率があるならやってみようと、直前でしたが受験を決めました。
学びの設計書には何を書きましたか?
西田 僕は本当に高校時代の実績がなくて……(笑)。《苦手だった数学を克服して好きになった》というエピソードで何とか400字を埋めました。大学で学びたいことには、経済学、心理学、数学を挙げました。
佐藤 僕の受けた学部も形式は同じで、生物学オリンピックの活動や部活で生物系の研究をしていたことを書きました。あとは好きな分野や、将来、仕事としてやりたい分野、そしてそのために学びたいことをまとめ、すごく学問肌(アカデミック志向)のこってりとした文章を送りました(笑)。
西田 具体的にはどんな分野が好きなの? 佐藤 一番は遺伝子工学です。DNAを上手いこといじったりするのが好きで、将来もそれを続けていきたいと思ってます。そのほかに好きなのは、微生物学や数理生物学。特に大学に入ってからは、生物より数学や、物理、化学ばかりやっています。将来、遺伝子工学をやる上で微生物学の知識などは役に立つと思いますし、できれば自分の興味を力にして活躍したいと思っています。ゲノム研究には停滞している課題がいくつかありますから、それらの解決のために研究者の人たちが使ってくれるツールを作れたらいいなと思っています。
大学でやりたいことについて、いつ頃から興味を持ち始めましたか?
佐藤 小さいころから生き物が好きで、力を入れていた自由研究では、プランクトンの研究や寒天培地の培養実験を行っていました。高校に入ってミクロの世界に触れるようになって生物学への興味が一層深まり、勉強していくうちに、遺伝子工学や数理生物学へと興味が移ってきた感じですね。 西田 僕は決まるのが遅かった。高校一年生の時は数学が好きで理学部に行こうと思っていました。ただ、「数学だけで生きていけるほど好きか?」と考え直し、工学部なども見て回りました。その時に、ある大学のオープンキャンパスで経済学も面白いなと感じ興味が出てきました。そこで入試形式も考慮し、入学後には何でもでき、合格可能性も最も高かった総合人間学部に決めました。
二次試験の対策や、受験後の所感を教えてください。
西田 二次試験の文系総合問題の小論文は、対策のしようがないというか。正直、特色入試で受かるとは全く思っていなかったため、小論文に力を入れるのもどうかと思い、一般入試の数学や理科の勉強をするくらいでした。当日は、勉強のことは置いておいて、遊びに行くついでのような感覚で試験を受けました。小論文は、一般入試なら点数にならないような支離滅裂なことを好き勝手書いてしまい結果は壊滅的だったのではないでしょうか(笑)。終わった瞬間はもうダメかなと。ただ、あまり対策もしなかったのだからこんなものだろうと頭を切り替えました。かわって理系総合問題では、数学を2問とも完答、理科の頭の体操の問題も、すっとアイデアが浮かび解答欄を埋めることができ安心しました。
佐藤 二次試験は小論文と面接でした。応生はまだ特色が始まって二年目で、過去問も一年分しかありませんでしたが、それには前提知識が必要とされる問題が少しあったため、出題されそうな環境系の生物工学について少し調べたりはしました。ただ、一般入試の英語のほうが心配でそちらに力を入れ、あまりしっかりとはやりませんでしたが。小論文は、単語が五つほど書いてあって、その中から一つ選んでそれについて述べよ、というとてもふわっとした問題でした(笑)。「遺伝子組み換え作物」を選び、専門書で読んだことなどを思い出しながら、けっこう上手く書けたんじゃないかなと思います。面接は対策のしようがなく、高校の先生に一度、立ち居振る舞いの確認をしてもらうくらいで、あとはぶっつけ本番で臨みました。実際にはいたって普通の面接で、学びの設計書に書いたことについて聞かれるくらいでした。答えのある問いではなく、自分の考えを深く聞かれる感じでした。受験生一人に先生7人でしたが圧迫感はなかったですよ(笑)。でもユニークな問いもありました。「人生で一番美しいと思ったものは何ですか」と聞かれた時には、標準化や規格化の概念だと答えました。基準を処理することで色々見えてくるのがいいなと思っていたからです。それを使って高校の時に力足らずで終わってしまった研究を改善するならどうしますか、とも聞かれました。最終的にはあまり失敗しなかったので、手ごたえを感じました。
西田 すごいですね。僕は、試験を受けた後、小論文が壊滅的だったためダメだろうなと思ってました。合格後に点数が開示されますが、それを見たら小論文は合格者の中で最下位でした(笑)。そのかわり理科は上から二番目でした。 佐藤 バリバリの理系だね。僕は逆に、センターの点数でひやひやしました。応生は二次試験通過後、センターの点数の基準をクリアしたら合格が決まりますが、リスニングと国語で失敗。二日目の試験開始前に一日目の自己採点をしたため、精神状態が最悪のまま数学を受けました(笑)。僕を含め二次試験の通過者は3人いましたが、最終合格者は一人でしたから、意外と鬼門だったみたいです。
合格が決まった時の気持ちを教えてください。また、合格後はどう過ごしましたか。
西田 発表の日は京大のプレテストを受けていて、その昼休みに結果を見ました。絶対無理だと思いながら画面を開いたら合格していたので、友達が受験ムードの中、一人だけで喜ぶのも差し障りがありますから、「また会おう」と言って次の試験を受けずに帰りました(笑)。合格したらラーメンを奢ってくれると約束していた友人に電話したため、そこから学校中に広まってしまっていて、翌日先生に報告した時には来るのが遅いと言われました(笑)。
合格後に、塾のチューターさんに今のうちにしたほうがいいことを聞いたところ、自動車免許とTOEFLと言われ、自動車学校に通って免許を取ったところまではよかったのですが、TOEFLの方は参考書を買ったところで終わっています(笑)。 佐藤 僕のところは二次の結果がもう発表されていて、センターの点数を加味しての最終発表だったため、二次の時とセンターの自己採点の時はとても喜んだ反面、最終発表の日は落ち着いていました。僕は携帯で結果を見ましたが、父は仕事帰りに大学へ見に行っていました(笑)。生物部の先生へは、東大の推薦入試に合格した友達と一緒に報告に行き、その足でカラオケにも行きました。合格後は、受験勉強で読めてなかった本を読み進めたり、ちょこちょこ遊んだりしていました。あと、生物学オリンピックの先輩のつてで、京大の生物化学の会というゼミに参加させてもらい、早めに京大に通い始めました。
大学生活はどうですか?
佐藤 サークルに3つ入っていて、平日はサークルに参加して夜ご飯を食べて、帰りは終電、という忙しい日々を送っています。大学に入ったらもう少し本を読む時間があるのかなと思っていましたが、そうもいかず…(笑)。大学の勉強は、自然科学系は大丈夫ですが語学に苦戦しています。英語の課題が多くて…。あとは、学生6人で自主ゼミもしています。生物系は独学で足りますが、やはり物数化は人と一緒に進むことでいい影響を受けると思いますので、時間がなくても参加してしまいますね。
西田 僕は最近、下宿を始めて、終電を気にせずサークルに参加したり友人と遊んだりするようになりました。サークルは生協系イベントサークルと、ダイビングサークルに入っています。ダイビングのほうは、週一で座学を勉強したり、プールで泳いだりして、免許を取ろうと頑張っています。勉強面では、自分も周りも、大学生ってあまりまじめに授業を受けないんだなあ、と思いましたね…(笑)。 佐藤 僕も出席を取らない授業は厳しい状況にある…(笑)。
大学で学び始めて生活を経て、学びの設計書に書いたことから興味の変化はありましたか?
佐藤 僕は数理生物に寄りすぎているかなと感じることはありますけど、ある程度ぶれずにやれていると思います。サークルにいる数理専門の先輩からの影響が強く、生物の記憶がだんだん薄れつつあります(笑)。
西田 僕は心理学と数学の授業はとれましたが、経済学は抽選に落ちてしまって…。初回の授業に参加して本当に面白いなと感じたので、後期は絶対に取ろうと思ってます。心理学は『ヒューマンインターフェースの心理と生理』という授業を受けていて、人間の推論方法などを学んでいますが、元々興味のあった文系寄りの心理学で、とても面白いです。あと、パソコン操作に少し強いため、後期には新しくプログラミングの授業を取ろうかなと考えています。小さいころ、初めて買い与えられたのがパソコンゲームで、やっているうちにほとんど操作を覚えましたから。
佐藤 わかるわかる、トラブルに自分で対応していくうちに使えるようになるよね。 西田 そう、ナンバーロックのテンキー入力を最初からできるようにするために、自分で調べて設定をいじったりして、知識や技術が自然に身についていました。そう考えると、自分のやりたいことに向かって、そこに行きつくまでに立ちはだかる壁を突破していくタイプだったのかもしれません。
大学入学後に特色生であることを感じる出来事などはありましたか。
佐藤 僕は応生の専門の授業が基礎的な内容だったため、受講していません。それもあって、他の学科の人には全然会いませんから、今のところそういう出来事はないですね。応生は3,4回生で実験三昧になるそうなので、おいおい関りはできるのかな、と。
西田 僕は一般と特色の垣根を感じたことはないですが、英語が苦手なうえに、一般入試を経てない分、英語の授業で周りより苦戦することはありますね。
佐藤 僕も英語で進められる授業では同じことを思う。
西田 もし一般入試を受けてたら、「英語解けてたかなあ」とか考えますよね。授業で当てられて答えられなくていじられたら、「まあおれ特色やから!」と開き直るようにしてます(笑)。あと、入学直後に他の特色生を探し出して連絡を取り、一緒にご飯に行く計画を立てたりもしているので、上回生も含めた特色生同士のコミュニティができればいいなと思っています。
 金 子璇さん
金 子璇さん医学部医学科
兵庫県立芦屋国際中等教育学校出身
特色入試を受けようと思ったきっかけは?
高校の先生の紹介でELCAS※1に高1の夏からの1年と、高2の夏からの1年で計2年参加していたのがきっかけです。ELCASでは最初様々な分野の先生の講義を聞いて、のちに参加者の興味関心にそった教室でさらに知見を深めるという経験をさせていただき、次第に京大に惹かれていきました。ただ自分の成績を考えると京大は少し厳しいかなと思っていたところ、ELCASでお世話になっていた先生に特色入試のお話を伺って、チャンスが増やせるならと受験を決めました。
もともと生物、特に人体や細胞への興味がつよく、大学ではそれらを勉強したいと思っていました。人体をやるならやはり医学科と思っていたのですが、学力的には厳しいものがありましたから一般入試の出願は医学部人間健康科学科か、農学部で考えていて、特色の医学科は受かったらいいな、というだめもとくらいの気持ちで出願しました。
出願要件に関して、科学オリンピック出場などは必須条件ではなく、高校の評定平均4.7以上とTOEFLの点数を持っていればいいということでした。出願自体は出しやすかった印象です。ただ、書類選考の時に、TOEFLの点数ではないかもしれませんが、何らかの足きりがありました。在籍していた高校が英語教育をしっかりしてくれていた学校だったので、私自身TOEFL自体はある程度自信があるスコアを持って受験に臨めました。
準備、学びの設計書
特色をちゃんと受けようと思ったのは高3の8月で、もちろん塾でサポートなどもありませんでしたから、自分でいろいろ情報を集めるところからスタートしました。学びの設計書には、様々な友人たちとの議論や発表を通じて、自分の考えをいかに伝えるかを学べたことがメインテーマにコミュニケーションという観点から、ELCASでの経験と高校での経験を2本柱に書きました。研究の動機としては、人体の仕組みについて、とりわけ、体内で起きる反応を挙げました。目に見えない病原菌が人体に侵入すると下手したら死んじゃうこともあって、そのプロセスを研究してみたいということ。また、参加した「女子中高生のための関西科学塾」というプログラムの中で、補聴器をつけた中学生が、うまく話せないながらも、プログラムを通して感じた楽しさを語っている姿に感動して、自分の研究が社会に反映されて、少しでも人の助けになればいいと思ったことも書きました。
書類自体は11月までには出来上がり、11/30の書類選考通過から過去問を解き始めました。ただ中身がすごく難しくて、わからないものばかり。自分なりに考えて、ネットで調べてみたり、本当に困ったところは高校の先生に相談してみたり。それでも正解が一つに決まらない論述問題が多かったので、これは答えが出せるか、よりも考え方をいかに理路整然に述べられるか、を見るテストなのだなと思うようになりました。過去問と平行して母が買ってくれた、科学的な思考、アイデアについての、京大の教授がお書きになった新書を読んでいて、それが面接のときに役立つこともありました。
試験
すごく緊張しました。でも過去問よりは簡単になったかな、という印象です。過去問は、今大学の授業で必死にやっていることが問題になっていましたが、私の受けたときは高校生の理科の知識によった問題が多くなっていたと思います。ただ思考プロセスを問う問題であるという感覚は変わりないです。
一日目を終えて、面接に進めることもわかったので、一段落していたのですが、面接が大変でした。4つ面接があり、一つはいわゆる普通の面接で、高校の成績や高校時の活動について。残り3つが特殊で、口頭試問のような形式です。まず20分で与えられた資料に目を通し、次の20分でその内容について教授2人相手にディスカッションという形式でした。内容は医療に関連することで、20分で準備するには深いテーマばかりでした。私は最後は普通の面接だったのですが、最後はクタクタでした(笑)。
入学して
医学部の特色は基礎研究、MD研究者育成のための入試なので、一度担当の先生と面接を行いました。私は研究者になりたかったのですが、「特色で入ったけど研究者になるかどうかはあなたの希望次第だよ」ともお話しいただきました。特色の学生はMD研究者育成プログラムに申し込んで採択されたら奨学金が得られるとも伺いました。後期からは、私も、プログラムの一環として、研究室にお邪魔して実験などを学ぶ予定です。
周りの学生との付き合いに関してですが、特色で入ると、最初のほうは、「特色生」という色眼鏡で見られて、特色だからすごいんでしょう、と言われますが、私は一般試験じゃ難しかっただろうという気持ちがずっとあるので、周りの学生のほうが勉強できてすごいと、やや引け目に感じた時期もありました。特色だって言いたくないとも思っていました。ただ、同じ京大に入ったらスタートは一緒なので、特色とか一般とかで比べる必要はないと思っています。なので、気楽にやってもらえたらいいと思います。はじめの頃は悩むこともありましたが、今は同級生と楽しく大学生活を送っています。
※1 ELCAS:京大が主催する高校生向けの体験型学習講座。文理問わず様々なコースが用意され、高校生が最先端の学術にふれる機会を提供している。
 武 優樹さん
武 優樹さん総合人間学部(理)
栄光学園高等学校出身
総合人間学部、特色入試を選んだ理由は?
高校まで関東に住んでいたのですが、高2の夏に東大・東工大などのオープンキャンパスをあちこち回りました。ですが学びたいものがしっくりこなかったんです。学生の発表を見せる大学が多かったのですが、僕はどういう学生になるかだけでなく、どういう先生から教わるのかも大事だと考えていましたので。そんな中、京大理学部のオープンキャンパスでは様々な先生が実際に解説をしてくれました。ひと通り解説が終わった後、直接先生と話もできて、京大に行きたいと直感的に思いました。
特色については母に教えてもらい、チャンスが増えるからと受験を決めました。学びの設計書など出願までに手間がかかりますが、なぜ自分がこの大学を志望しているかはっきり整理できる良い機会でもありました。また、関東からの受験なので宿泊や試験当日の気持ちの作り方など、一般入試に向けてのリハーサル、練習としても役に立つかなと。
出願の準備を進める中で、理学部でなく総合人間学部(以下、総人)を受験しようと決めました。総人なら自分のやりたいことができると思ったからです。防災とメディアなど、一見すると別の学問分野を同時に学べるのが総人です。僕自身、根っからの理系というよりも高校でも社会が好きでしたし、一つの分野に絞らずいろいろやりたいと思っていたので、そういう意味でも総人が合っているかなと思いました。
学びの設計書に書いたこと 試験について
小さいころから地震や津波など自然災害に興味がありました。東日本大震災をきっかけに関心を持ち始め、大学に入ったら地学をやりたいなと漠然と思っていました。学びの設計書には自然災害に対する防災とメディアの融合ができないかということを書きました。どんなに科学が発展しようと、日本に住んでいる以上、自然災害と共存していかなければなりません。そこで考えるべきは減災です。私は今発達しているソーシャルメディアなどを生かして減災ができないかと考えました。例えば、地震が起きて津波が起きるとなったとき、ドローン空撮を使い、津波を目で見えるよう報道したらどうなるのか。今のテレビでは陸からの定点カメラしか映していません。それは見る人にとって危機感がない。ドローンなどを用いて今起きていることが臨場感をもって視覚的に分かれば、危機感を得て助かる人も増えるかもしれません。
少し話がそれますが、僕の母校では「歩く大会」という全校生徒で長距離を歩く企画がありました。しかし、コースは僕が中1の頃から全く変わっていませんでしたのでそれを変えてみようと思いたち、僕と同級生たち、それに一つ下の代の後輩たちと有志で組織を立ち上げ、実地調査をし学校にコースを提案するところまでしました。こういったことを学びの設計書の高校での活動として書きましたね。僕が在学中には叶いませんでしたが今年からコースの変更が実現するようです。
今年は学びの設計書による足きりがなく、また面接もなかったので試験一発勝負だったのがつらかったですね。去年総人の特色を受けたのは15人でしたが、今年は43人で倍率8倍、合格は厳しいなと思ったので、その点は気楽でした。あくまで二次試験の練習のつもりで挑みました。しかし試験ではあるのでやっぱり緊張しましたし、一週間前からは食欲もなくなり少し病みそうでした(笑)。
文系総合問題の負担が大きかった。準備も含めてかなり不安でした。今まで小論文を書く機会も多くなかったし、過去問を解いても時間内に解ききったことがなかったので、びくびくしながら本番を迎えましたね。なんとか10分前に書ききりました。
入学してみて、将来のこと
学びの設計書で想定していた勉強と現状の勉強はかけ離れていません。前期は学びの設計書で書いたことに関連するような授業を取っています。高校までで学べなかった地学を重点的に学んでいるのですが、様々な授業の内容がリンクしていることや、同じような内容でも分野の違う先生だとこういう風に見るんだなという気づきがあり、面白く過ごしています。今のところは思った通りに学べている気がしていますね。
将来的にはメディアと防災を繋げていきたいと考えています。いかに学んだことを社会に還元していくかを考えているので、マスコミ、報道関連の企業に就職できたらと考えています。今の社会は、情報の伝え方によって全てが決まってしまうようなところがあるので、学んだことを活かし、メディアを通じて防災に貢献していきたいです。







