今なぜ、アントレプレナーシップ学環なのか?
京都産業大学が、未来の「当事者」となる学生のための新しい大学教育を始動
大学教育への危機感を背景に、真にこれからの社会に必要な人材を育成しようと設立された京都産業大学。時代を先取りする数多くの取組で、今日の大規模総合大学としての地位を築いてきました。創設60年を期に満を持して開設を計画しているのがアントレプレナーシップ学環。その名もずばり、起業家精神と行動力を養う分野横断型の新学部。「建学の精神に立ち返りながらも、新たな教学改革をリードすべく構想した」と話す同学環長就任予定者の中谷真憲先生に、設置の背景や狙い、教育の概要について伺いました。
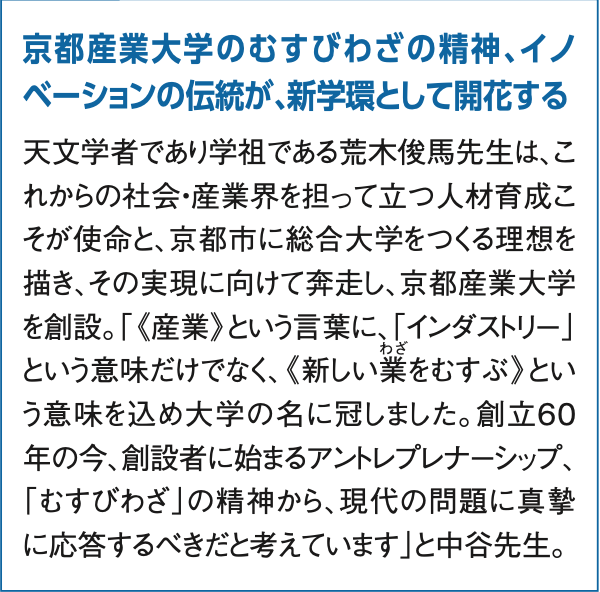

中谷 真憲先生
~Profile~
学環長就任予定者/法学部教授
1993年京都大学法学部卒業。1999年京都大学大学院法学研究科博士課程修了。修士(法学)。京都大学大学院助手、立命館大学非常勤講師を経て、2001年京都産業大学専任講師。認定NPO法人グローカル人材開発センター専務理事兼事務局長。共著に『公共論の再構築』など。滋賀県立膳所高等学校出身。
これからの社会に真に必要な「人」の育成にむけて
大学っていったい何を学ぶところだろう?この問いは、「何のために大学に行くのか?」と同じものです。受験生なら誰しも、そして大学生の中にも時にそう思う人は少なくないと思います。
私はこれまで、専門である公共政策学の観点から、大学での学びやそこからのキャリア形成に強い関心を持ち、就職氷河期と言われた時期に、グローバル化の波が押し寄せる中で、グローバルな視野を持ちローカルの課題解決に挑戦できる人材育成のための「グローカル人材開発センター」※1 を、京都の5大学の有志と立ち上げ、産官学連携によるキャリア教育プログラムの作成や、新たな資格制度※2 の創設にかかわってきました。
当時と今とでは、学生の就職状況は大きく異なりますが、「大学で何を学ぶのか」「何を身に付けるのか」、あるいは「どう学ぶのか」といった本質的な問いに対して、いまだ明確な答えが示されているとは思えません。就職状況が劇的に改善したことで、その問いの持つ大事な意味さえ薄れてしまわないか心配です。
アントレプレナーシップ学環は、その問いに真剣に向き合い、これまでの実践から得た知見やネットワークを活かし、産官学連携、分野横断で応えるべく構想しました。AIとの共存も現実となる今こそ、これから自分は何をなすべきか、座学と実践との往還の中で、自分ごととしての「自己開拓型(自分を深く掘り下げる自己探究型)」の学びを通して、それを探究し、イノベーションの意義を知り、アントレプレナーシップ(起業家精神)、本学で言う「事(コト)起こしの精神」を養い、主体的に人生設計ができる人材の育成を図ります。
それを実現するために用意したのが、「学部等連係課程」※3 としての新しい教育組織です。複数の学部連携により、新たな学部相当の教育を創り出す、新しい大学教育の仕組みです。学びを連環させることから「学環(がっかん)」と呼びます。私の所属する法学部と、経営学部、現代社会学部が連携し、社会課題の探究・解決や起業には欠かせない幅広い知識やスキルを、分野を横断しながらも体系的に学ぶことができます。卒業時に付与される学士号は「ビジネス」です。
※1 現在は認定NPO法人グローカル人材開発センター
※2 GPM(グローカルプロジェクトマネージャー)、初級地域公共政策士
※3 令和元年(2019年)8月に学校教育法施行規則及び大学設置基準等の一部改正により、新たに設けられた「学部等連携課程実施基本組織に関する特例」により、複数の学部や研究科が連携して教育課程を編成することが可能になった。
やりたいことをデザインし、4年間没頭する学び
知識やスキルの修得のために効果的な学びとは、明確な目標に向けた、主体的、積極的な学びであることは誰しも認めるところだと思います。そのためには、自分が必要だと判断した知識やスキルが学べる授業を、自分で選べるに越したことはありません。
つまり、自らの学びをコーディネート、デザインし、座学だけではなく、学んだことを学外で実践して、再び大学で学べば、その知識・スキルは確実に定着します。それを私は、大学での学びを「自分ごと化」すると言っています。自分のやりたい目標のために、「あの先生の授業はここで使える」などと、自ら学ぶべきことをデザインできるような仕組み、それを可能にするのがアントレプレナーシップ学環です。
象徴的な科目が、2年次からの『セルフ・カルチベーション』です。演習科目の一つではありますが、「自分自身で目的や学修する内容をデザインする」自走型が特徴です。まず、スタートに当たっては、自分の目標と授業デザインを教員にプレゼンします。教員はそれらが、本人の目指すプロジェクトに結びつくか、取り組む意義を学生がしっかり自覚しているか、「自分ごと化」しているかどうかを丁寧に見極め学生にフィードバックします。
このようなやり取りを重ねて、一人ひとりの授業デザインが決まっていきます。そして、各自のプロジェクトや事業遂行のため、大学を飛び出し、その結果を発表します。探究したいこと、やりたいことに没頭する学びです。
実績ある「アントレプレナー育成プログラム」がベースに
『セルフ・カルチベーション』などのベースとなっている取組が、令和5年度に始動した全学部生のための「アントレプレナー育成プログラム」の授業群。文理融合型で、全10学部の教員が担当。定員を上回る受講希望がある人気プログラムです。
ここでも私は『アントレプレナーシップ演習A』を担当しています。昨年度は特にチャレンジングな取組として、豊田通商株式会社(トヨタグループの総合商社)と連携し、EVスクーター事業の展開をテーマにしました。
授業をよりリアルにするために、実物のスクーター数台と充電スタンドを提供してもらい、**JAF(日本自動車連盟)**には安全講習をお願いしました。この試みは好評で、学生たちは、キャンパス内外で実際にEVスクーターに乗って乗り心地を体感し、それを基に新規事業を考えました。最終的に提出した事業案には、数字の裏付けも入れましたから、豊田通商からは「期待する水準をはるかに超えたもので、学生の実力の高さに驚いた」と、高い評価をいただきました。

一拠点総合大学「ならでは」
学環の基盤科目として開講するのが、「アントレプレナーシップ」「ビジネス探索」「ビジネスデザイン」の3つの科目群。これらの中には、『科学技術と未来社会』や、『食とテクノロジー』といった、最新のテクノロジーがどのような社会を創り出す可能性があるのかを探究する斬新な科目もあります。
また韓国、オーストラリア等の協定先に出かける『海外起業フィールドスタディ』や、『交渉力とプレゼンテーション』『スタートアップ・ワークショップ』なども新設します。
これらの取組を支え、加速するのに強みを発揮するのが、すべての学部が一つに集結する「一拠点総合大学」。あらゆる分野の専門家たちが一か所に集まっていますから、分野横断の学びを実現できます。学環の開設後には、キャンパスのそこかしこで、刺激的な交流が日々起こるのではないかと期待しています。
定員はわずか30名。しかし、もっと多くの仲間がすぐそこに。
アントレプレナーシップの輪を広げよう
定員は1学年30名、4学年合わせても120名の少人数体制です。自己開拓型の学びを実施するには、きめ細かなサポートが必要だからです。
ただ、「アントレプレナー育成プログラム」や、経営、法、現代社会の3学部による『展開科目』の授業では、様々な学部の学生と一緒に学びますので、仲間の数はかなり大勢になります。学部・学環、学年を越えて多様な学生同士の交流の機会が多く、アントレプレナーシップ育成の学びが相乗効果を発揮できる可能性は大いにあり、それが、日本の大学の学部教育にもインパクトを与えられないかと期待しています。
高校生へのメッセージ
「アントレプレナーシップ学環」は、大学で本気に学び行動したい人に応える場所です。高校時代に探究学習に力をいれていた人、何かにチャレンジしてみたいと思っているような「冒険者、求む」です。きっと、ワクワクするような4年間を過ごすことができると思います。
またここでの経験を社会に出てからも活かし、困難な課題にも前向きに挑戦することで、これからの社会・産業界で広く求められる存在になれるはずです。







