時計遺伝子の発見で、薬理、栄養、運動のすべてに時間軸を
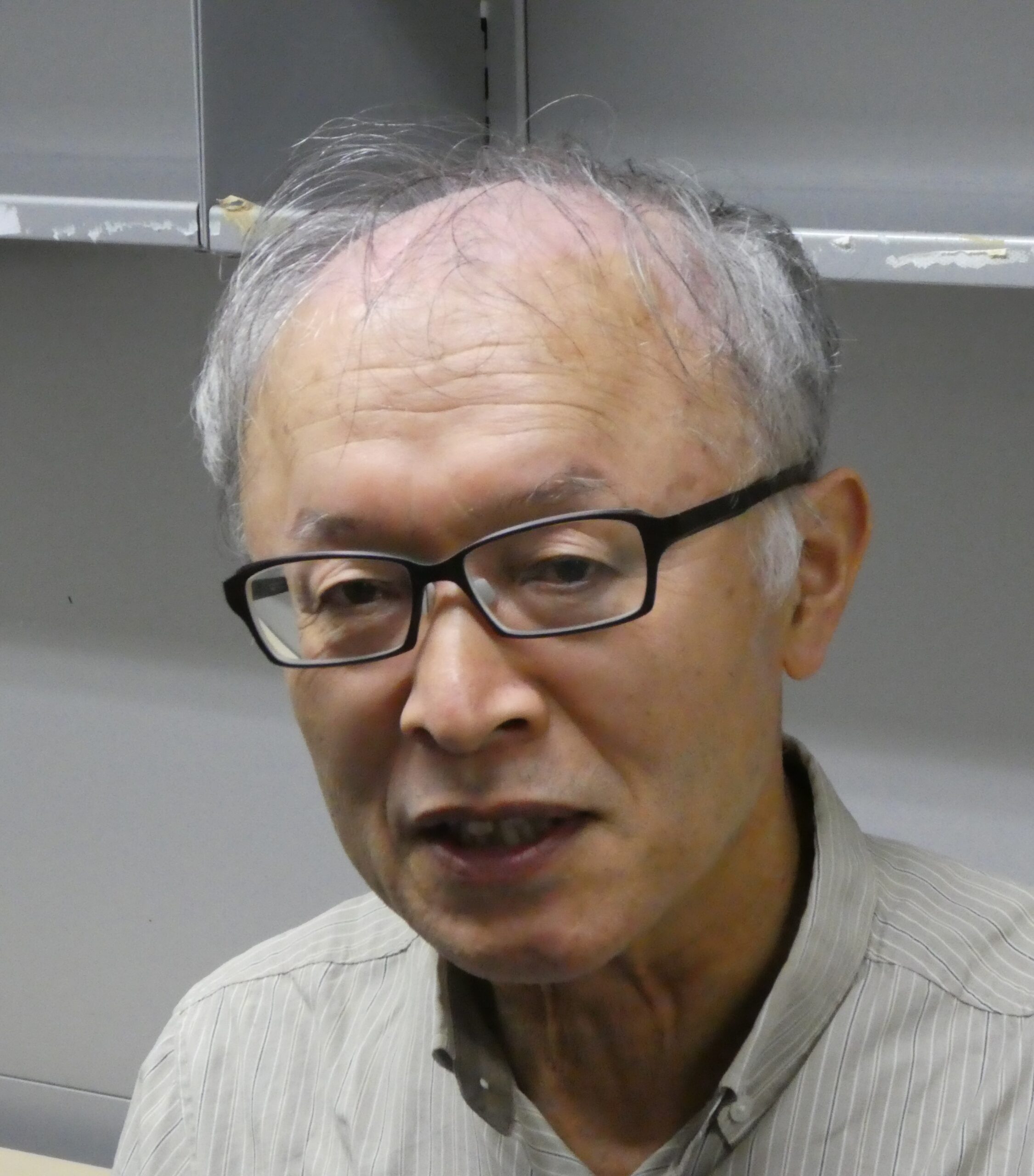 早稲田大学理工学術院教授
早稲田大学理工学術院教授先端生命医科学センター長
柴田 重信 先生
~Profile~
早稲田大学理工学術院教授。先端生命医科学センター長。九州大学薬学部卒業、同大学院薬学研究科博士課程単位取得退学。薬学博士。著書に『時間栄養学』(女子栄養大学出版部)、『体内時計健康法』(共著/杏林書院)など。福岡県立福岡高等学校出身。
近年、イワシやサンマの人気が上昇している。それらに含まれるDHAやEPAが健康にいいとされているからだ。児童・生徒には頭が良くなるというアピールもされる。しかし「いつ食べればいいか」となると答えられる人は少ないだろう。「どんな栄養を摂ればいいか」を一歩進めて、「いつ摂ればいいか」について科学的な示唆を与えようというのが時間栄養学。現在その最先端を走る早稲田大学の柴田重信先生に、最新の知見と今後の展望についてお聞きした。
時間栄養学の生まれた背景と、目指すもの
時間栄養学(クロノニュートリション:chrono nutrition)は、時間生物学(クロノバイオロジー)を学問的裏付けに、栄養学を再構築していこうというもので、私が専門としてきた薬理学における時間薬理学と同じ発想に基づいている。3、4年前から研究者も増え関心も高まるが、これには昨年のノーベル生理・医学賞の受賞対象となったショウジョウバエの時計遺伝子の発見から、1997年においてヒトを含む哺乳動物での類似した時計遺伝子の発見が大きく寄与している。
生物の体内リズムを司るメカニズムとして知られる体内時計。その在処が、脳の視交叉上核だけでなく、脳の他の場所や、各臓器や筋肉、さらには皮膚にいたるまで存在していることがわかったからだ。以降、視交叉上核にある時計は全体を司るという意味から「中枢時計」、あるいは「主時計」、脳の他の場所にあるものを「脳時計」、首から下にあるものを「末梢時計」と呼んで区別する。
体内時計の周期は生物によって異なり、人間の中枢時計では一日が24時間より少し長い24,5時間(概日リズム)。そのため一昼夜に正確に対応するには、毎日0.5時間の誤差を調整(リセット)する必要がある。この調整には中枢時計では朝の光などの光刺激が、それ以外では、中枢時計の指示に加えて、食事、特に長時間の絶食後の食事が強く関与する。具体的には消化器官系へのインスリン分泌刺激による調整だ。ここに時間栄養学が求められる背景と、成り立つ根拠がある。
私は長年、薬理学を専門としてきたが、健康科学、予防医学の観点からは、薬より、より日常的に摂取する食と栄養がより重要と考えるようになった。ただ栄養学が扱うのは化学物質の集合体で、薬のように単品ではないため、薬理学のように、血中濃度等を見て、薬効、どの成分がどれだけ吸収されて効果があったかを簡単に見ることはできない。さらに食となると、扱うのがその集合体だからもっと複雑だ。調理の仕方によっても《効き方》は変わってくる。たとえば水溶性植物繊維の多いゴボウを、ささがきとナノフード(微細加工)のそれぞれの形でネズミに与えると、後者は腸内細菌を強く活性化させるが、前者はあまり役立たない。また薬理が《飲み方》を含めるように、《食べる行為》も含めたり、その時の体調なども考慮したりするとさらに複雑になる。これらの点を考えると「時間食物学」と呼ぶ方が正確かもしれない。 現在、主な研究としては、食・栄養、食品機能成分が体内時計をいかに刺激し活性化させるかと、体内時計の特徴を踏まえた三大栄養食品、食品機能成分などの摂り方、その最適な時間の究明の二つを目指している。
特定機能性表示食品をいつ食べる?
後者ではいくつかの特定機能性表示食品について、「いつ食べればいいか」をいくつかの企業と共同研究している。
機能性表示食品は医薬品ではないから、厚生労働省や消費者庁からすれば「いつ食べてもいい」ということになる。ただ《機能》を、《生体と相互作用して何らかの効果をもたらすこと》と考えると、生体がダイナミックなリズムを持つ以上、薬と同様、インタラクションの仕方、タイミング等によって効き方も変わると考えるのが自然だ。薬との境界を設けることは難しい。《機能性表示》というものを止めない限り、「いつ食べればいい」かの問題は避けて通れないのではないだろうか。
実際、大手を中心にいくつかの企業では、データ収集と検証が進んでいる。たとえばDHAを含む魚製品に力を入れている水産加工会社では、オメガ3※1は朝の方が血中濃度は上がりやすいというデータを持っている。リコピン(トマトに含まれる赤の色素)を主成分とする製品の開発に力を入れている食品メーカーでは、その血中濃度は夕方より朝の方が上がりやすいとしている。これらの企業では、こうしたデータを持っておかないと、消費者の質問に答えられずビジネスにならない。
※1 オメガ3系脂肪酸:ALA(α-リノレン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサン塩酸)の総称。
朝食の重要性に新しい裏付けを
体内時計にいかに刺激を与えるかという観点から注目しているのが朝食。一般的に朝食は、昼食や夕食に比べてそれまでの絶食時間が長いため、末梢時計に与える影響は大きい。あるヨーロッパの研究グループは、同じ光刺激の下で食事の時間を起床から5時間後にすると、起床後すぐに朝食をとった場合より、中枢時計はそのままなのに、末梢時計が2.5時間も遅れることを実験で突き止めた。これは中枢時計が通常通り光でリセットされても、末梢時計のリセットが5時間も遅らそうとしたから、その中点で2.5時間になったものと理解されている【下図Wherensら,2017】。見方を変えれば、朝食は体内時計に大きな影響を与えるという意味で、あらためてその重要性が再確認できる※2。
にもかかわらず、おおむね朝食2:昼食3:夕食5というウェート配分が世界的な傾向だ。そこで私たちは、運動をしない夜にとる夕食には無駄が多いと、夕食の比率を4に減らし、朝食を3に増やすことを提案している。起きて何時間までを朝食とするかの定義はさておき、朝食の重要性をもっと認識してほしいからだ。ちなみに上のようなケースについて私たちは、体内時計がそろって目覚めていないという意味で、「朝食時差ボケ」と呼んでいる。朝食抜きで学校へ行き、午前中ぼーっとしていることがあるとしたら、それは低血糖によるものではなく、時計そのものが朝を示していないかもしれない。
※2 文部科学省は「早寝早起き朝ごはん」の国民運動を展開。平成18年には「早寝早起き朝ごはん」全国協議会も設立されている。
遅い夕食には「分食」、「攻めの間食」で対応
忙しい現代生活では、夕食でも昼食から時間が大きく空いてしまうことが少なくない。すでに見たように夕食は、三食の中で一番ウェートが高いため、それまでの絶食時間が長いと、食事による刺激が強くなって血糖値が上昇し、体内時計が目覚めて夜型になるリスクがある。これは同時に肥満になるリスクでもある。これを軽減するのが「分食」。遅い夕食と昼食との間に軽く何かを口に入れて血糖値を上げておくと、夕食による血糖値の上昇が抑えられる(「セカンドミール効果」)。塾・予備校へ通っている場合は、その前におにぎりなどの主食を食べ、帰ってからおかずを食べる――「攻めの間食」を勧めたい。
現代社会は夜型化が日に日に進んでいるが、基本的な設計は朝型が基準。これからシーズンを迎える入学試験も、朝からが一般的。学校や大学のカリキュラムやテストの多くも2時間目がゴールデンタイムだから、朝型の生活を維持しておくことが何よりも大切だ。すでに夜型になってしまった受験生は、少なくとも一週間前からは――3日では厳しい――朝型の生活に戻しておきたいもの。朝は光を浴び朝食をしっかりとって体内時計を目覚めさせ、夜はブルーライトを極力避け、カフェイン含量ドリンクを避け、体内時計を覚醒させないようにすることだ。
コラム①
受験生へのアドバイス
朝食では何を食べる?
朝食では炭水化物に加えて、脂質、タンパク質の三大栄養素をバランスよくとることが大事。私たちの実験では、でんぷん質、魚油、タンパク質は、いずれもインスリン機能を促したり、ある種のホルモン分泌を介して体内時計を覚醒させる。タンパク質については、運動を伴うことで成長に必要な筋肉を作るという役割にも注目しておく必要がある。食後に通勤・通学で体を動かす朝食は、効率よく筋肉を作るためにも重要だ。小・中学生約1万人を対象に行っている食育に関する調査では、「朝食抜き」より、朝食でたんぱく質を摂る割合が少なく、朝食でたんぱく質をしっかり摂った児童・生徒の方が、勉強や運動が好きと答える割合が高いことが明らかになっている。
コラム②
高校生へのメッセージ
私はもともと、うつやアルツハイマーの治療に関心があり、体内時計との関係で脳を調べていた。しかし体内時計がすべての細胞にあることがわかってからは、筋肉や骨、皮膚、さらには免疫系との関係、また運動と時間についても研究するようになった。皮膚の免疫では、化粧品会社との共同研究もしている。最近は、生活の夜型化や肥満の増加傾向を調べるために、ITベンチャーと共同して時計遺伝子のビッグデータを回析してクラスタリングすることも計画している。分野融合や異業種連携は、今後ますます進むと予想される。高校時代からいろんなものに興味を持っておくとともに、大学では一つのものを究める、自分の得意分野を固めておくことも忘れないでほしい。







