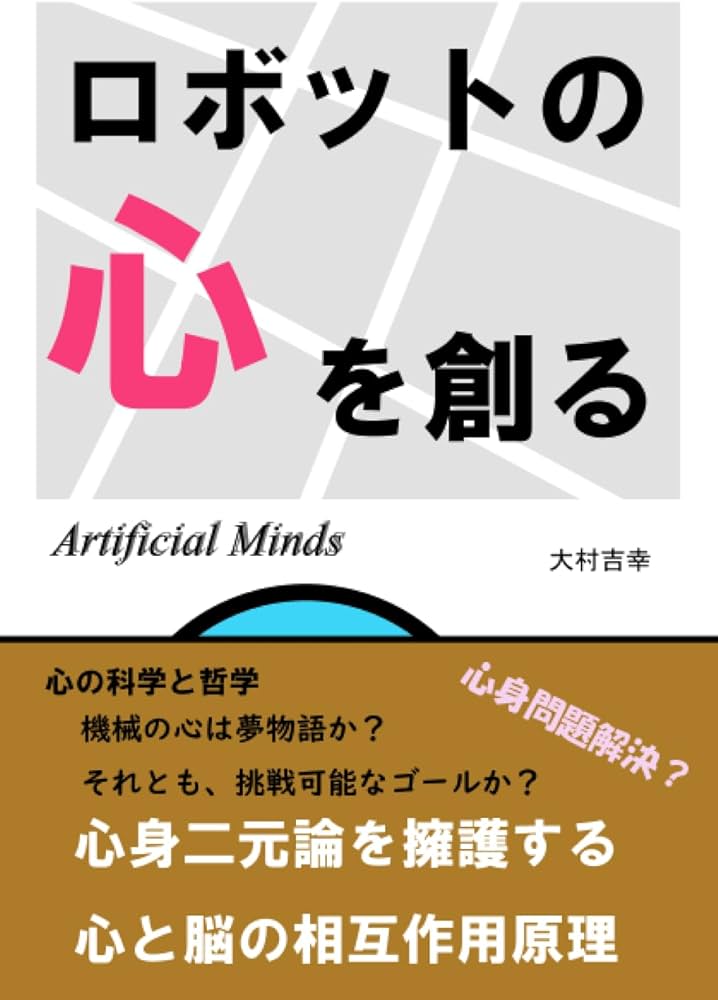
~Profile~
京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大 阪産業大学他非常勤講師。著書に『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食につい て』(人文書院)、『快楽の効用』(ちくま新書)。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。
英国のヒューマノイドロボットのAmecaをご存知だろうか。唇を動かして人間と会話し、手振り身振りで話しながら自然な感じで表情を変え、瞬きし、求めに応じて作業ができるロボットだ。自分がどのように描画するかを説明してくれるので、では可愛い猫の絵を描いて、と頼めば、猫が人に好かれる理由や仕草について話しながら猫の絵を描いてサインをし、私の絵が気に入らないのなら多分芸術が理解できないのだと思う、と冗談を言う。踏み込んだ哲学的な内容の会話も多言語でできる。
AIは人間の「心」を理解し始めているのかという質問に対して、まだ完全に理解することはできておらず、今後自分たちAIは、言葉だけではなく感情や経験を共有することが重要で、それにより更なる進化が期待できると答える。また、人間と関わり合う知能を作りたいのであれば、単にデータを収集して判断させるだけでは足りない。AIも適切に理解し応答するためには身体は欠かせない、と答え、自分も誰かを抱きしめたり、本当の風を感じたりしてみたい、想像の中でしかなかった世界を感じ、世界とそのあらゆる不思議を体験するために身体が欲しくなってきた、と話す。
滑らかに受け答えするAmecaには「自分」という意識があり、意思を持って話しているようにみえる。機械が大規模言語モデルで予測された言葉を生成しているだけだとしても、人間同士の会話だっておおかた自分の中で集積されたものから予測したものであり、それでお互いをわかり合っていると思いこんでいるのだから同じようなものではないか。そうすると、この先、人間と同じようなロボットが生まれて来ないとも限らない。
本書の著者は、東京大学工学部機械情報工学科在学中にロボコンに出場、現在東京大学で、心を持って人のように世界を理解するロボットの開発を目指して研究を続けている。人の身体に近いロボットを開発するうちに、身体の感覚と運動を計測して数式化することを重視するようになり、脳と身体の関係、意識や「心」はどこにあるのか、などについて追求することになる。
ロボットが意識を持っているように「みえる」のと、意識を持っているという事実とは違う。それに、ロボットが意識を持っているのかどうか、どのように確かめればいいのだろう。そして、意識と心は同じなのか、違うのか。心とは何か。
人間の脳ー神経系は物質だ。意識や心は物質ではないから実在するかどうかさえ計測できない。私が猫の絵を描くとき、物質である脳が猫の絵を描くという命令を下すのか、意識が脳を起動させるのか。
身体=物質と意識/心=非物質の問題、すなわち心脳問題は、古くから哲学や科学の分野で考えられてきた。
本書は、身体・脳/意識/心について様々な理論を検討しながら、現在の物質一元論に疑問を呈し、「心」を考えようとする。はっきり言って慣れていないと読むのが難しい。後半の「仮想の対談」や丁寧な用語解説から読む方が面白いかもしれない。
心を持つロボットを創りたいという研究者の気迫が伝わり、ひるがえって読むものも、知能とは何か、心とは何か、人間とは何か、ということを考え出すだろう。







