脳と心、そして「私」という謎への旅
リチャード・レスタック(著) / サイモン・ブラックバーン(編)
ディスカヴァー・トゥエンティワン
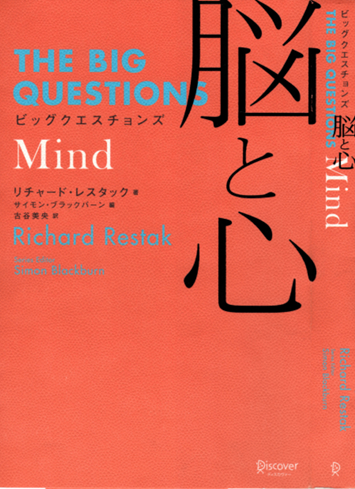
意識の不在と「生きている」ことの意味
あなたは、眠っている時どこにいるのだろう。もちろん、他者から見ればあなたの身体はベッドの上に横たわっている。だが、眠っているあなたはそれを知ることができるだろうか。
知覚や随意運動、記憶や思考をつかさどる大脳が休んでおり夢も見ないノンレム睡眠時は意識がないので、そもそも「〈自分〉がどこにいるか」という問いは出てくるわけがなく、知る以前の状態だ。もし、このまま目覚めないとしたら、自分は生きているのか、死んでいるのかわからない。眠ることはこの上なく気持ちがいいのに、こう考えると眠っている時は、〈自分〉がどこにもいないという意味でいわば「死んだ状態」と同じと言えるかもしれない。
そうすると、ずっと意識のない状態で横たわっている人には、経験を積むことはないのだから人生はないと断じてよいのか(多分、そうではない)。人生とは、経験の積み重ねによる記憶と意識の集積なのか。だが意識とは、身体と離れてあるわけではない。意識とは脳が作り出したものだ。その脳は、体中に張り巡らされた神経系の中枢であり、内部では物質が運動している。意識がなくても、身体は生きている。では、感情はどこから生まれてくるのだろう。心、というのはなんなのだろう。
20の問いから探る「人間」の正体
こうした素朴な問いは、実はとてもとても難しいテーマであり、古来より考えられてきたし、現代では哲学や医学、動物行動学、心理学、物理学、ロボット工学などあらゆる方面に展開される。人間とは何か、という問いであるからだ。
また、例えば俗に言う植物状態や重度の認知症の場合、主体というものがあるかどうか、受精卵の遺伝子操作の是非や胎児に人格があるのかどうか、といった、医療倫理などが絡む現実の問題にも繋がってくる。意識や心とは何か、それがあるというのはどういうことか、ということを考えるには、考えるということそのものが意識であるので、つまりは自己言及のパラドックスが付きまとうので厄介だ。
神経科医の手になる本書は、いわゆる心-脳問題を多角的に、分かりやすく語ったものである。著者は、脳と心(そして魂)の探求に、20の問いを立てて取り組んでいる。
- 心は体なしに存在できるか
- 脳はどのようにして生まれたか
- 感覚とはなにか、意識があるとはどういうことか
- コミュニケーションに言語は不可欠か
- 脳の中の「私」とはなにか
- 知識とはなにか
- 共感や利他主義はどう生まれたか
- 愛とはなにか、機械は脳をダメにするのか…
決定的な答えが、出されているわけではない。おそらく出されようもない。ただ、読者は「心」の不思議に改めて驚くとともに、進化の過程で「心」が生まれてきた意味に思いをはせるのではないか。挙げられた問いを出発点として、人間について「あなた」が考えていくための手掛かりを本書は豊かに与えてくれている。人間について、そう、「あなた」について、だ。
評者 Profile
雑賀 恵子 (さいが けいこ)
京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪産業大学他非常勤講師。
【主な著書】
『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食について』(人文書院)、『快楽の効用』(ちくま新書)。
大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。







