 京都大学 学際融合教育研究推進センター
京都大学 学際融合教育研究推進センター准教授 宮野 公樹先生
Profile
1973年石川県生まれ。2010~14年に文部科学省研究振興局学術調査官も兼任。2011~2014年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科学。南部陽一郎研究奨励賞、日本金属学会論文賞他。著書に「研究を深める5つの問い」講談社など。
先日、理工系の院生と、芸大の院生とが交流するイベントに参加しました。まず理工系院生による研究紹介があり、続いて研究室を見学。その後に芸大院生による作品の展示を見るという流れです。この手の「科学x芸術」企画は特に珍しいものではありませんが、今回、実際に参加していろいろと感じることがあったのでお話ししたいと思います。結論から言うと、科学と芸術とでは、それぞれ修養の仕方が違うことをあらためて感じたということです。
まず理工系院生の研究説明を聞いて感じたことは、どうしても仕方がないことなのですが、それが「自身の研究の説明」というよりも「所属する研究室の研究紹介」ではないかということでした。「僕はこういう研究をしています」とプレゼンするものの、それは所属研究室が脈々と続けてきた研究山脈の一部。使っている理論や装置などは、彼が研究室に所属する以前から存在しているもの。つまり、彼の仕事(研究)は、研究室に配属されたときに教員から与えられたテーマの追及や、付随する理論や関係装置を使いこなすことなのです。独自性は、その研究を遂行する上での工夫として現われる。苦労し苦悩し、あてがわれた研究テーマをなんとか無事に(できることなら最速で)クリアすることが腕の見せ所となるわけです。
これが良いとか悪いとか言いたいのではありません。科学の研究、特に実験系ではえてしてこういうことが多いのです。今日の科学は極めて複雑化、高度化、さらに付け加えるなら「技術化」しており、院生自身が自分の研究テーマ、すなわち「学術的な問い」を持つためには、膨大な経験を含めた基盤的予備知識が不可欠です。そしてそれらを身につけるためには数年(で済めばいいほうですが)かかる。こう考えると、理工系院生には「自身の研究を説明して」ではなく「この研究室を選んだ理由をプレゼンして」というお題のほうが良かったのではないでしょうか。
理工系院生のプレゼンおよび研究室見学が、いうならば<説明>だとすると、芸大院生の作品の展示会からはむき出しの<感情>が感じられました。「私そのものです」と言わんばかりに並べられた作品と対峙すると、鑑賞する側も気持ちを揺さぶられます。例えば、この彫刻のこの部分はなぜこの色でこの形なのか。それに明確な根拠や理由などありません。しかし、「あれもちがう」「これもちがう」と、何百回、何千回と試した後に選択されたその色・形状からは、「これ以外にありえない」という意思、覚悟のようなものが感じられます。言うならば、芸大院生との対話は想いのぶつけ合い。「僕はあなたの作品からこう感じる」と伝えるだけで、まどろっこしい知識や前提条件を一切抜きにして、彼・彼女たちと自然観、人間観、世界観をやり取りできる。非常に濃密な、精神性の高い時間を持てたのです。ただ、物足りなさを感じる作品もないことはありません。もしかしたら、作品に凄みをもたせるためにはそれ相応の人生経験が必要なのかもしれません。ただしそれは、生きてきた時間の長さによるものではなく、どれだけ他の精神(人でもモノでも本でも)と本気の交わりをしてきたかによるものだと思います。
今回強く思ったのは、科学も芸術も、本来、同じ根っこから生まれたはずなのに、現代ではなぜこんなにも別個のものとして扱われるのかということです。科学とてその始祖は、芸術と同様、この世界に対する驚きだったはずです。だからこそ、科学にしろ芸術にしろ、それを究めようと思えば、「そもそも科学とは」「そもそも芸術とは」という視点と思考を持たなければならない。さらにいうなら、自分を見つめるもう一人の自分を自分の中に存在させておくこと。そうでなければ、本当に心から自分自身で納得できる研究、作品を生むことはできないのではないでしょうか(続く)。
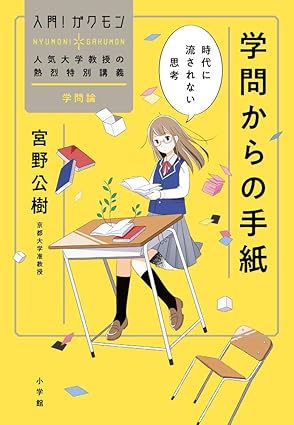
研究と趣味の違いや、勉強と学問の違いなど、ぜひお楽しみください。







