 東京藝術大学学長 日比野 克彦先生
東京藝術大学学長 日比野 克彦先生
~Profile~
1958年岐阜市生まれ。1982年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。卒業制作で第一回デザイン賞受賞。1984年同大学院美術研究科修了。在学時にはサッカー部に所属。1982年第3回日本グラフィック展大賞、1983年第30回ADC賞最高賞、1986年シドニー・ビエンナーレ、1995年ヴェネチア・ビエンナーレ出品。1999年毎日デザイン賞グランプリ、2015年文化庁芸術選奨芸術振興部門 文部科学大臣賞受賞。1995年東京藝術大学美術学部デザイン科助教授。1999年美術学部先端芸術表現科の立ち上げに参加。2007年同学部教授。2016年から同学部長。2022年4月から現職。岐阜県立加納高等学校出身。
リズムが合ったダンボールとの出会い
美術の世界を志したのは高校1年の時。クラスでみんなと一緒に大学進学を考えていた時に、「絵が好きだから、美術で自分を表現できたら、生きている実感を深く味わうことができるだろうな」と考えたことが、進路決定につながりました。
高校を卒業して最初に入った大学は多摩美術大学。当時、多摩美からは人気のシンガーソングライター、荒井由実さんが、武蔵美(武蔵野美術大学)からは芥川賞受賞作家の村上龍さんが、といったように、ジャンルを超えたスターが生まれるなど、私立の芸術系大学は、1980年代のジャパンアートアズナンバーワンと言われた時代を予見させるような輝きを放っていました。
結局僕は、翌年、東京藝大のデザイン科に入り直すわけですが、ここでは1・2年生のうちに、基礎的な創作活動を経験するために様々な素材に触れます。3年生で自分なりの表現を探すことになるわけですが、鍵になったのが素材やテーマ選び。周りの教員から教わるのではなく自分で探す。というのも、芸術系の学びでは、例えば教員が40歳なら学生とはほぼ20歳違うけれど、同じ表現者で、美術史から見れば同時代作家になる。テクニック的なことを教える・教わるということはあっても、大人と子どもとか、学生と教員と区別することにあまり意味がないからです。大事なのは、自分で何をどうやって生活の一部にしていくか、でした。
そこで僕が選んだのがダンボール。
歌を歌うにしても、走るにしても、喋るにしても、人それぞれの持つリズムというものがある。だからそれに合った素材に出会えれば、夢中になって楽しい時間を過ごせる。楽しい時間とは苦労する、しないに関係なく、その素材と対話している時間で、そんな時間を経て気付くと「作品」ができている。
僕にとって、そんな息の合う素材がダンボールでした。中でもそのスピード感。石を削るのだと、1ヶ月はかかる。焼き物も乾かしてから焼くのに2ヶ月かかる。鉄にしてもそうです。色合いなども含めて自分にしっくりくる、それが段ボールだったのです。




アートの社会的な機能とは?を大学から社会へ、日本から世界へ発信したい
2027年に開学140年を迎える東京藝術大学。
国内唯一の国立の総合芸術大学で、岡倉天心※1、伊沢修二※2など、
明治を代表する思想家、教育者、芸術家などが創始者や歴代校長に名を連ねる。
ミッションは、わが国固有の芸術文化の振興と国際社会への発信に加えて、
世界の芸術文化の発展に寄与し、
国際舞台で活躍する芸術家、研究者を輩出すること。
このような伝統の中で、2022年4月、現代アート専攻(先端芸術表現)から
初の学長になられたのが日比野克彦先生。
先生の考えるアートとは、藝大の新たなミッションや芸術教育について
お聞きするとともに、高校・大学時代におけるアートとのかかわり方、
さらには、日本のアートや芸術系大学に興味のある海外の若者にも
メッセージをいただきしました。
※1 1863年~1913年、日本の思想家、文人。前身である東京美術学校の設立に大きく貢献した。第2代校長。
※2 1851年~1917年、明治・大正期の日本の教育者、教育学者。近代日本の音楽教育、吃音矯正の第一人者。前身である東京音楽学校の創始者の一人で初代校長。
東京藝大の伝統とこれまでのミッション
本学ができたおよそ140年前は、明治維新の完成期に当たり、西洋から様々な文明を取り入れた日本は、生活スタイルも含めて大きく変わった。ヨーロッパをモデルに、大学をはじめいくつもの高等教育機関も設置された。その役割は、和魂洋才と言われたように、主に欧米の知識・学問の移入・紹介だったと言っていい。
芸術に関する学問、研究機関としてスタートした本学も例外ではなく、現代美術とか西洋美術といった学問・研究の文脈の中でアートを捉えてきた。それはアートを芸術と訳した時点から始まっているのかもしれない。《学問として》の芸術、その教育・研究は以来、伝統となり、僕らも受けてきた西洋美術史などの授業にまでつながる。
しかし芸術、アートは本来、学問ではない。人間が元々持っている感情が創出するエネルギーの結晶であり、表現者だけではなく受け取った人、鑑賞者や集団の心も揺さぶるものだ。当時まで日本に受け継がれてきた絵画・彫刻、舞踊・音楽、文芸も立派な芸術だし、世界的には、今の人類の絵画の歴史は1万6000年ほど前の洞窟壁画にまで遡る。ものを作る源となる人間の感情は太古からあり、学校で描き方を習ったり、デッサンの勉強をしたりしなくても立派な壁画は描ける。

.png)
未来に向けて東京藝大が目指すもの
《学問として》入ってきた芸術についての教育・研究は、伝統を重ねる中で《縦割り》の弊害に陥りやすい。例えばお笑いなどの芸能も文化の一つだが、《芸術》としては認められてこなかった。しかしリレーショナルアート(relational art)、会話をはじめ人間関係も、生活のすべてはアートであるという概念が生まれてきたように、今では文化も芸術として捉えるのが当たり前になっている。
このような芸術――以下はアートと呼ぶが――の歴史、概念の変化について、私たちがきちんと伝えてこられたかというと少し不安だ。「藝大って入るの難しいですよね」「上手じゃないと絵じゃないですよね」、あるいは「知識がないと美術館行ってもつまらないですよね」というようなメッセージの方が強く受け止められてきたのではないか。美術館に行って絵を観たり、コンサートを聞いたりするだけがアートにかかわることではないが、今、あえてそう言わなくてはいけないのは私たちの責任でもある。
僕の考える藝大の使命は、芸術の教育・研究やトップアーティストの育成だけではない。
アートとは本来何なのかを社会に対して声高に、しっかり発信し、それを通じて、アートを社会の課題解決に役立てることのできる人材を育成し、その価値を認めてくれる社会の構築に寄与したい。もちろんこれは大学だけでできることではないから、小・中学校、高校の美術教育と一緒に取り組む必要がある。
STEAMについて
理系人材育成、あるいはイノベーション創出が、大学や産業界に求められる中で、STEM(科学Science、技術Technology、工学Engineering、数学Mathematics)にA(Art)を付けたSTEAMをキーワードにしようという考え方がある。STEMだけでなくA、つまりアートが大事だと。これは理系の研究や技術開発において、今後は、より豊かな発想力や想像力、観察力や描写力が必要である、そこでアートシンキングというものを起爆剤にしていこうということだろう。しかしアートが文化や日常生活とは不可分なものだと考えれば、あらためてそう言う必要はないのではないか。
星を見て、あれは何だろう、宇宙ってどのようにしてできたのだろうと想像力を働かし、イメージを膨らませる。それが宇宙の解明へとつながっていく。人はなぜ死ぬのかという好奇心から、医学においても遺伝子レベルまで研究が進む。これらが科学技術の進展へとつながってきたことは言うまでもない。アート、アート的なものは科学的な態度、思考の土台、基盤でもあって、後付けするようなものではないと思う。
反対に言えば、何がアートなのかについては、藝大だけでなく、教育全体、地域全体、社会全体で考えていかなければならない。
アートは心の揺らぎだ『100の指令』で意図したこと

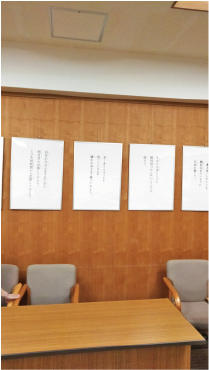
この部屋には、上のように、発想の転換を促すような短いメッセージの書かれた額を懸けている。その一つひとつは著書『100の指令』から抜き出したものだ。人が何かをイメージするのは、多くは言語によるものだし、反対にイメージを伝える時にも言語化することが多いから、それを遊びにしたのだ。特別に突拍子もない指令ではないけれども、それに応えていく、あるいはそれを自分でも作っていく中で、いろんな感覚が刺激されていく。
僕はこれこそがアートだと考えている。
アートを見て人は感動するが、例えば油絵なら、ゴッホ、ピカソの絵も、物質的にはキャンバスに絵の具が塗ってあるだけ。それを見て感動するのは、絵がすごいのではなく、見た人がすごいからだ。感動とはこちら側、人間の中で、その気持ちが動くことだ。
だからアートって、揺らぎ、心が揺らいだ時に生まれるエネルギーみたいなものとも言える。
誰でも気持ちが揺らぐ時がある。夕焼けを見て「ああ綺麗だな」と一瞬目が止まる。旬の果物を見て、美味しそうだなと思う、映画を見て感動する、音楽を聞いていて、なんとなくいいメロディだなとか。外的な刺激によってふと心は揺れ動く。それがアートのきっかけ、というよりそれ自体がもうアートって呼んでいいと思う。
美術館や音楽会には、みなそういう揺らぎを体験したくて行く。でも、自分でスイッチが入れられるようになれば、別に行かなくても、名画や名品を見たり名演奏を聴いたりしなくても、「なんかいいな」という世界に入れる。確かに、自分はこれから心を揺り動かされに行くという心の準備があると、人間は暗示にかかりやすいから、行った先で感動しやすい。しかしその暗示力みたいなものも、自分でコントロールできれば、心は動かせる。もちろん人間には、人がいいと思うものをいいと思えると安心するという集団心理も働くから、もっと総合的な分析も必要ではあるけれど。
いずれにせよ物だけがアートなのではない。それはこちら側、観る側、鑑賞者の側にある。絵画や音楽は、そのスイッチを押すきっかけでしかない。『100の指令』を出した意図もここにある。
考えてみれば、目の見えない人、耳の聞こえない人も美術や音楽と無縁ではない。心は動くから、いろんなものをきっかけにして、これがアートだと感じることができる。最近、白鳥建二さんという全盲の美術鑑賞者が話題だが、彼の話を聞くと、やはりこの確信は深まる。
アート、近未来
情報通信技術やメディアの急激な進展で、アートの在り方もここ3年から5年ぐらいの間で随分変わってきている。
その結果、生徒、学生が教員の知らないことを知るようになり、先人が、もう先生ではないという、これまでと違う関係性が生まれてきている。鑑賞の仕方も、創作や表現の仕方も変わってきている。作家の中には、VRゴーグルを使って鑑賞できる「バーチャルアトリエ」で製作する者も出てきている。そこでは重力のある空間では作れなかったものもできてしまうし、サイズも関係なくなる。これからの3年から5年ぐらいでは、こうした作品は急激に増え、これまでのリアルの、物質文明で生み出された作品と同じぐらいの量になるのではないか。その結果、現実の空間とバーチャルの空間がどんどん滲んできて、お互いに価値を交換できる時代になるかもしれない。
とはいえ、現実の空間はなくならないし、身体は年老いてはいく。
このようなこれまで誰も経験したことのないような時代が訪れたときに、どういう心の動きが現れてくるのかが、とても楽しみだ。藝大にとっても、これまでの140年とはまた違う140年になるのは確実だと思う。
高校生へのメッセージ
私のように志望校選びをきっかけにアートを考えるのもいいと思うが、受験生の多くは、アートは受験とは関係ないから、できるだけ入試で問われる教科の勉強に力をいれようと考えるかもしれない。しかし、アートは大学へ行ってから、さらには年を取ってからでも始められるもの。この記事を読んだ人が、今は受験勉強に力を入れて、「大学へ入ってから、絵を描こうとかギター弾こう」と考えてもいいと思う。アートがいつも身近にあると、人生はもっと豊かになる。回りとの競争の中で、評価や数字と対峙するのもいいけれども、傍らに数値化できないような領域で過ごすすべを持っていると、最近よく言われるウェルビーイングではないが、精神的にも豊かな人生を送れるのではないか。アートのエキスパートにならなくてもいい、でもアートが身近にある人生はぜひ送ってもらいたいと思いますね。
海外の高校生へのメッセージ
昨今、中国から日本の芸術系の大学へ進学を希望する人たちが増えている。そのための予備校もできていると聞く。大学院進学が中心だが、本学も例外ではない。
では東京藝大、というか日本の芸術系大学のどこに魅力があるのか。とっさにアニメが思いつくが、他にも理由があると思う。
一番の理由は、日本が安全であり、また学費もアメリカやヨーロッパに比べて安いこと。コンテンツについては、日本は、長い歴史に培われた文化の中から最先端のものも生まれてくるという、不思議というか独特の国で、アニメ以外にも様々なものがあること。確かに日本には、長い歴史の中で中国から取り入れたものが多いと思うが、それを独自に消化し進化させてきたところに特徴がある。
言語の問題も大きいかもしれない。言語は、英語で喋ると英語の思考になり、日本語で喋れば日本語の思考になるといったように思考回路を作るが、歴史や地理的な環境の影響を強く受けて成り立つ。日本は小さな島国で、同じような小さい島国は他の地域にも様々あるが、アジアのファーイーストという立地、南北に長いといった地形に特徴がある。そのため四季折々の表情が豊かで、詩や俳句には季節を表す様々な言葉がある。これは独特の感情や心の揺らぎ方を表現できるから、大きな魅力の一つになっているのではないか。もっとも日本がなかなか国際化できない原因の一つにこの言語の問題があることも確かだが。
かといって日本人がこれまで海外文化を拒絶してきたわけではない。漢字を中国から取り入れ、それをデフォルメして平仮名にし、西欧の言語・概念もカタカナを使って取りこんでいる。拒絶はせずに取り入れて変容させ、そして混ぜていくのが得意だ。この融合力もまた魅力の一つになっていると考えられる。









