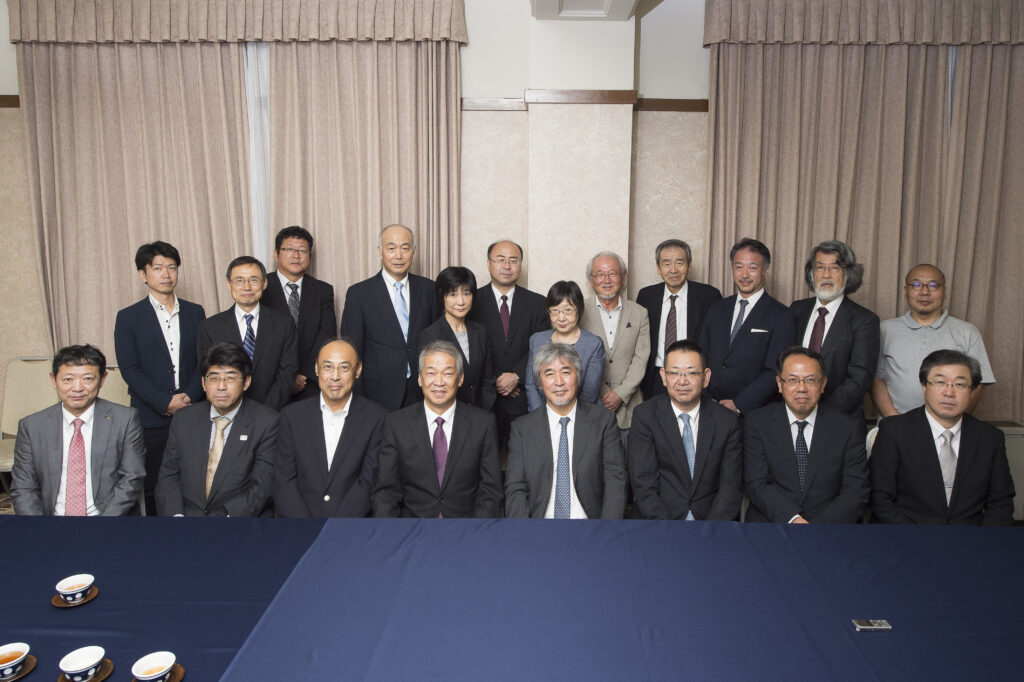

京都大学総長 山極 壽一 先生
~Profile~
1975年3月 京都大学理学部卒業
1977年3月 京都大学大学院理学研究科修士課程修了
1980年3月 京都大学大学院理学研究科博士後期課程研究指導認定退学
1980年5月 京都大学大学院理学研究科博士後期課程退学
1980年6月1日 日本学術振興会奨励研究員
1982年4月1日 京都大学研修員
1983年1月16日 財団法人日本モンキーセンターリサーチフェロー
1988年7月1日 京都大学霊長類研究所助手
1998年1月1日 京都大学大学院理学研究科助教授
2002年7月16日 京都大学大学院理学研究科教授
2009年4月1日 京都大学教育研究評議会評議員(2011年3月31日まで)
2011年4月1日 京都大学大学院理学研究科長・理学部長(2013年3月31日まで)
2012年4月1日 京都大学経営協議会委員(2013年3月31日まで)
2014年10月1日から現職
東京都立国立高等学校出身
2009年11月19日に始まり、通算9回目となった本座談会。この間、秋入学に始まり、大学入試改革についての議論も加速しました。今回の大学入試制度改革には、いくつかの伏線と様々な背景、要因が考えられますが、その一つに、若者の間に広がる過度に正解を求めたり、決められたレールの上を進むことを良しとするようなマインドに対する、産業界や大学の危機感があったことは否めません。大学入試改革にどこまでインパクトがあるかはともかく、高大接続、記述式、多面的・総合的評価などのキーワードは、この文脈の中に置くことで初めて意味を持ちます。今回はグローバル社会の中を逞しく生きていくのに欠かせない「失敗を恐れず挑戦する心」、「挑む心」を育むために、大学は、高校は何を課題としてその解決にどのように取り組んでいるのかを軸に話し合っていただきました。(10月12日学士会館にて)
京都大学総長と首都圏進学校校長座談会 高校と大学の対話を深めよう
京都大学のこの1年
山極: 大学は今、様々な改革を加速させていますが、その柱は、国際化、産学連携、自律的な資金の確保の三つです。
国際化は教育面では学生のモビリティを高めることが目的です。京都大学でも100を超える大学と大学間学生交流協定を結び、単位互換の仕組みなどを整備することにより、一旦は京都大学に入りそこから海外へチャレンジするという選択肢を用意しています。
様々な留学の形があってもいいということで、「おもろチャレンジ」(京都大学海外渡航支援制度一鼎会プログラム)を昨年から始めています。期間は3週間以上で、行先は大学に限りません。学生自身で企画し、行先の選定、事前交渉など全て自分でやってもらいます。30件を目途に、審査に通れば上限30万円を支援します。昨年は115名の応募の中から31件採用しましたが、行先にはアフリカなども含まれています。今年は昨年より多い143件の応募があり、予想より学部生が増え、しかも女子が多くなっています。一昨年から開始した「学生チャレンジコンテスト」は、学生自身が活動計画を立てて、それがおもろかったらwebに掲載し、一般の方々からクラウドファンディングで資金を集めるというものです。他に「学際研究着想コンテスト」というのもやっています。
高校生に大学からのメッセージを伝えるのも非常に重要であり、毎年、高校生に模擬授業を提供する「サマースクール」を、また都道府県の教育委員会等との連携による「サイエンスフェスティバル」も行っています。サイエンスフェスティバルでは、選ばれた高校生のチームには京都大学に来てもらい、発表して競ってもらいますが、高校生とは思えないようなアイデア、取組もあります。理学部から始まった「ELCAS」では、本学の教員が月二回、週末に高校生たちへ大学と同じような内容の講義や実験・指導を行っています。講義・実習を行う基盤コース19分野に135名、研究室に配属され少人数制で実験・実習を行う専修コースに18分野28名が参加しています。また、今年度からは分野を人文系にも広げています。
特色入試は、当初ハードルが高いのではと避けられる傾向もありましたが、熱意があれば、能力以外の要素も選考の対象になると説明を続け、徐々に高校や高校生の理解が広がってきたと実感しています。入学してきた学生がどれぐらい伸びるか、大いに期待していますし、今後さらに枠を広げていきたいと思っています。
産学連携では、日本の指定国立大学法人制度の最初の3大学に選ばれました。自然科学分野だけではなく、人文社会科学の牽引者となることが期待されているというのが意外でしたが、元々京都学派と言われるベースがありますから、きちんと人文社会科学系の学問から立て直し、それを国際的に発信していく核を作りたいと考えています。その一環として掲げたのが、「吉田カレッジ構想」で、日本語で講義やセミナーを受けられる留学生を募ります。また、優秀な学部学生を海外から募り、日本人学生と混住する寮を現在建設中です。現在、大学院生中心に2,200人ぐらいの留学生を、数年のうちに4,000人以上にしようという計画です。
その他、リカレント教育として、京都の文化芸術系の国公私立大学と組んで10大学で、「京都アカデミアフォーラム」を立ち上げ、この秋には東京丸の内に専用のオフィスを開設しました。
挑む心をどう育むか――参加校は今
杉山: 今年も16人京大にお世話になりました。「吉田カレッジ構想」など、京大のグローバル化は着実に進んでいると感じました。今日のテーマでもある、チャレンジする若者を増やすために、大学もいろんな仕掛けをしていると感じると同時に、高校では、まだまだそれが大きな課題として残っているのではないかという気がしています。全般的な印象では、今の生徒には失敗することを恐れたり、安定志向に走ったりする気質がありますが、それは保護者にもあると思います。それを打破するにはいろんな仕掛けが必要ですが、本校は男子校ということで、「無理難題に挑戦しろ」と様々な取組を行っています。その一つが50キロを7時間で歩く古河強歩大会。こういう取組に仲間と一緒に挑む中で次第にチャレンジするマインドが育ってきます。また一年中、スポーツ大会をしています。クラスマッチで教員チームも必ず入りますが、とても強く、自分たちを乗り越えてこいとばかりに盾になっています。このように教員が矜持を示すことも大事です。学校として様々な仕掛けを作り、その上で保護者の意識も変えるよう働きかけることが大事だと考えています。

稲垣: 3年生の京大への志望は増えていて、来年度も20名弱は受けてくれると思っています。進路選択には、先輩たちが戻ってきて話をしてくれるのがとてもいい刺激になりますが、京大生は研究系の話や、興味のあることをいろいろやっていくのが面白いという話をします。今日もまた「おもろチャレンジ」のお話をお聞きして、学生にすべて自分たちで考えさせるという考え方を、大学で取り入れてくれているとのことで、高校側としては非常にありがたいと思っています。 本校の体育祭も生徒だけで作り上げていく一大プロジェクトです。3年生が、2年のこの時期に引き継いで一年間かけて生徒だけで作り上げていく。引継ぎのための膨大なマニュアルにも見るべきものがあります。生徒だけで作り上げていくことで、見えない力の育成に大きく寄与していると考えています。それがあるからこそ、体育祭が終わると急きょギアを入れ変えて受験勉強に臨みます。校長としては、失敗を恐れる子たちが少し増えてきているように感じていますから、ハードルをもう一歩越えるために何を仕掛けていくか、それがこれから非常に重要になってくると思っています。

吉野: 今の子どもたちには失敗を恐れ、親が敷いたレールの上を素直に進む子が本当に多い。下手するとそのまま真っすぐ、周りを見ないまま、失敗しないままで大人になってしまう場合もある。そこで15年ほど前から、思春期の前半に当たる中学3年間では、家庭でやるべきさまざまな後押しを、生徒指導、生活指導として学校でも援助しようということになり、今ようやく軌道に乗ってきたところです。 具体的には、まず3日に一回、席替えします。いろいろな価値観を持つ子とぶつかりあい、親から与えられた自分の価値観だけが正しいのではないことに気づかせ、それを乗り越えて価値観の違う他者と一緒に行動できるような環境を作ることで、チャレンジしながら失敗を恐れない子に育ってほしい。またアサーション(自己表現)トレーニングも取り入れていて、コミュニケーション能力を高めることで、クラスを越え、学年を越え、学校を越え、さらには国境を越え、文化、歴史観の違う国の人と、明日の平和な世界を一緒に作っていく能力が育つのではないかと期待しています。 本校の考えるグローバル化とは、国際競争に負けてしまうから頑張れと言うのではなく、価値観の異なる隣の子と一緒に行動できる資質を伸ばし、世界の中で活躍できるように自分の枠を外に広げていくこと、一歩踏み出してチャレンジできる素養を育てていくことだと考えています。これは、入学段階で「もう少しチャレンジしておけば良かった」などと考えている生徒の意識変革にもつながると思います。
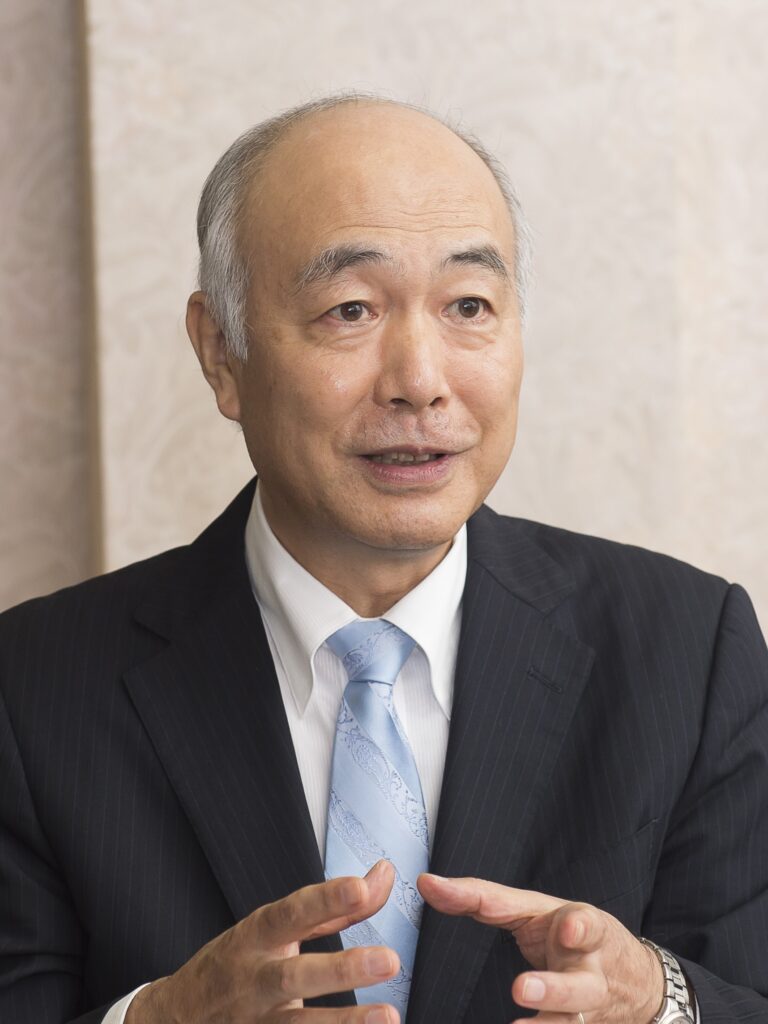
柳沢: 開成では、中学1年生は1学期の学校行事や部活の経験を通じて、ロールモデルとしての先輩を見習うことで、自主性、自律性を養います。進路選択についても、教員は口出ししません。最近は海外の大学に行く卒業生も増えていますから、その影響からか、学校全体で今年は40名強が海外のサマースクールに行っています。部・同好会活動は70ほどあり、おおむね自分がやりたい部活は揃っています。OBによる億単位の寄付金を基金にしたのが「ペン剣基金」。自分がしたい研究を、大学の教員のように申請書を書き、審査を受ける。誰でも、つまり中学1年生でも、教員でも参加できます。審査を通ると平均20~30万くらいのお金が使え、最後に報告書を出すことが必要です。チャレンジできる場、機会がたくさんあり、生徒たちは親とべったりとくっついているのが恥ずかしいという感覚を持つようになりますから、一番寂しい思いをしているのは母親かもしれません。

梶取: 本校は自由と自立を重んじる学校と言われていますが、昔に比べると生徒ははるかに小粒になってきています。また男子校とはいえ、以前よりはひ弱になっている。これには親との関わり方の影響が大きいと思っています。 今や高校も大学もグローバル化一色ですが、私は、海外に限らず、外に出ることを「広義のグローバル化」と捉え、そういう機会を増やし、まずは生徒の足腰を鍛えたいと思っています。授業だけでなく、校外学習など様々な体験をさせながら、英語の4技能の強化だけでなく母語の4技能をきちんと身につけ、何にでも挑戦できるタフな生徒を育てたい。まだ模索中ですがそう考えています。
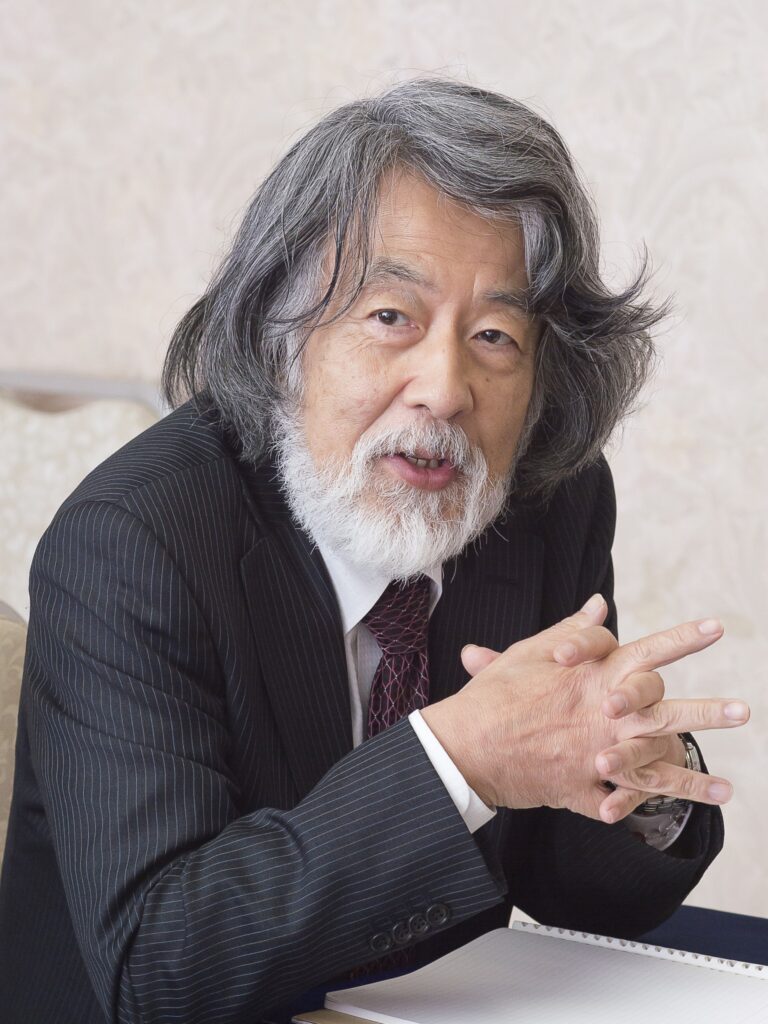
山極: それには個人指導、一対一の対話が必要で、そういう環境を作ることも大事だと思います。どれがフィジビリティが高いのかを見抜く力などは、経験のある人に少しだけサジェスチョンをもらうだけでずいぶん違ってきます。
梶取: 将来、シンギュラリティが来ると言われる中で、単に技術を学ぶだけならおそらく学校はいらなくなる。やはり専門集団の大人がいて、いいこと悪いことも含め、いろいろなことを学べてこそ学校だと思います。
百瀬: 確かに今の生徒、家庭は成功志向が強いと思います。また、反抗期を迎えないまま卒業していく生徒がいるのではないかとも懸念しています。母親が敷いたレールに乗り、冒険しない。他流試合も怖がる。反面、SSHで課題研究に取り組む生徒はタフになっていきます。そこで今は、課題研究を理数だけではなく、人文社会系にも広げています。1年から開講し、何にでも挑戦する態度を育むきっかけの一つにしてほしいと。生徒には、家庭事情や経済的な問題を踏まえつつも、いろんな体験をさせ、より深く考える必要のある機会を作って、一歩先へとステップを踏んでいってほしいと思っています。 本校では生徒の動機付けについても工夫していて、その一環として大学の先生だけでなく卒業生、企業の研究所などからもゲストを迎え、話を聞かせてもらっています。

山極: 動機付けにはやはり、時代の高みに上り、先を見る必要があると思います。具体的な目標を立てるまでは必要ないと思いますが、産業界でもアカデミアでもいいから、そこで頑張っている人たちの話を聞くことはとてもいいと思います。
佐藤: 「おもろチャレンジ」に一番興味を持ちました。特に院生よりも学部生にもっとチャレンジを促す仕掛けを考えられていることです。この春、千葉高に赴任して、まず大学に入り、大学院に入ってから頑張ればいいと考えている生徒がいることが少し気になりました。おもろチャレンジに応募してくる学部生は、将来はともかく、とりあえず今はこれをしてみたいということでしょうか。

山極: 学部生の企画には、フラダンスを習いにハワイに行きたいなどの、将来の研究やキャリアと全く結びついていないものもあります。自分の思いを第一にして、裸一貫で行ってやり遂げてくる、それは将来の目標に直接結びつかなくても大きな力になるはずです。高校現場では誤解もあるかもしれませんが、われわれは学部生を大学院で囲い込みたいとは思っていない、可能性を伸ばすためには他へいってもらってかまわないと思っているからです。
佐藤: 高校生にもこういうチャレンジをさせたいですね。大学に進んで、自分の研究をもっと深めていくのが、「チャレンジする」ということではないかと思います。本校でも総合学習での調べ学習や、「千葉高ノーベル賞」などがありますから、こういう形でどんどん研究にチャレンジし、その上でこういう大学に行きたいというようになってほしい。まず大学に入っておいて、チャレンジは大学院でしよう、あるいは海外に出ようと考えているのを、高校や大学でも「チャレンジする」としたいと、今日のお話を聞いて感じました。

平: 男子生徒には、マニアになる脳というか、興味・関心が湧くと深掘りする子が多いですから、知識をいかに定着させるかより、いかに刺激を与え続けるかが学校の役割になると考えています。そのための一つが国際交流であり、もう一つが「教養総合」です。後者は2004年から始めたもので、高1、高2で学年の枠を取り払って土曜日に2時間、基本的には少人数授業で、人文、語学、芸術、スポーツ、科学、それとリレー講座に分けて、各学期で一つ取ることになっています。必修で、高1高2で全部で6種類取ることになります。当時大学では教養教育が縮小され、一方、大学入試に特化した効率的な勉強を重視する生徒が増えてきていたため、教養教育を高校で担おうとわれわれ教員が始めました。やはり学校は、刺激を与える装置を用意するのが一番大事だと思っています。

山極: スポーツと違い、学問の力は複線で伸ばしていかなければなりませんから、一つのことばかりやるのは考えものです。ここで修めたことが別の場面で活きるわけですから、将来、方向転換できるような幅の広さをもつことが学問の豊かさ、可能性につながると思います。
杉田: 「おもろチャレンジ」は本校のSGHの取組とよく似ています。「ローカルな生物資源を利用してグローバルな製品として発信しよう」というテーマの下、市場調査から海外フィールドワークまで行います。海外に出たり、会社を起こしたりなど、かつての高校生からすれば夢のようなことが、手の届くところにある。このような取組がきっかけになり、チャレンジするための壁は低くなっているのではないかと思います。ちなみにこのプロジェクトに参加した生徒の一人は特色入試で合格させてもらいました。京大へは毎年6名程度で行っていますが、興味を持つ生徒も相当数いますから雰囲気もあっているのかなという気もしてきました。
武内: 挑む力ということでは、ご出席の公立校同様、生徒には第一希望は譲らないというようなところがあり、浪人率は高いほうだと思います。また勉強だけでは人間の幅を広げられませんから、学校生活の中でできるだけいろんなことに挑戦できるように、いろいろな仕掛を用意しています。典型的なのが「一高祭」と「歩く会」、そして「一高オリンピック」と呼ぶ体育祭です。どれも、生徒が実行委員会を作り自分たちの手で作り上げていき、教員はサポートに回るだけです。かかり集団とか小集団の中で、失敗も成功も味わうことで、自信がついてくる。自信がないと何事にも挑戦できませんから、学校行事、部活も含めて学校の中で、自己肯定感や自信をつけさせ、挑む心を後押ししていくのが公立学校のやり方ではないかと思っています。 卒業生の声は、やはり生徒の進路に大きな影響を与えます。学部生、特に1年生が、どれだけ入学後に充実感を感じているか、逆に言うと、大学が学部生をどれだけ大切にしているかが、必ず次の世代に如実に反映されてくると思っています。
山極: SGHやSSHで学び、野心を持って大学に入ってきても、それにきちんと応えられないようではまずいと思います。生意気な学生は生意気なりにいろいろなところで芽を出してほしいですから、まずは1、2回生でそのためのチャンスを与えたい。1回生の野心をどれだけ伸ばしていけるかがこれからの大学のミッションでもあると思います。
岸田: 3年前から京大ツアーを始め、今年は40名参加しました。本校の雰囲気は体育祭と文化祭の違いはあれど湘南高校と似ているかもしれません。文化祭では、3年生は80分の演劇を2日間で8回こなします。お客さんも今年は二日間で1万1717名来られました。1年生のアンケートを見ると、大体6割が文化祭に惹かれ、あと部活動にもということで来ています。その点では同質の生徒が増え、昔に比べ全体的に小粒になってきているかもしれません。ただ、文化祭を引き継ぐ際には、毎年改良していこうとしていますから、まだまだチャレンジ精神は旺盛だと感じています。SSHやSGHの指定は受けていませんし、学校で3年間過ごしたいと海外留学にも行きたがらない生徒が多いですから、その目を、いかに外に向けさせるかが一番の課題だと考えています。

竹鼻: 昨年度「宇宙リチウム問題」の研究で京大総長賞を受賞した卒業生が、7月の「土曜未來講座」でその話をしてくれました。実は4年前にもこの卒業生に「理系の先輩に学ぶ」という「土曜未来講座」をしてもらい、その影響もあってか、今年は浪人生も含めて、京大に9名入学させていただきました。女子は自信が持てない子が多く、100%自信がないと手を上げられない。そこで、憧れの先輩と接したり、生徒同士で学内外での取組を報告し合ったり、「自分もできるかも」と思わせる仕掛けをたくさん用意しています。海外研修は30年ほど前から行っています。価値観の違いに気づき、親元を離れて他人の家で過ごすことで自立が図れます。英語の上達より、苦労を味わう経験の方が大切な学びだと感じています。3年前から3ヵ月留学も始め効果を上げています。

山極: いよいよ女子寮を改築します。きれいになり収容力も増す。女子学生の割合も増えています。とくに工学部の建築やかつての土木系(地球工学科)ですね。もともと医学系は多いし、教育でも女子の比率が高くなっています。理学部も私のころは300名のうち8名だったのが今は一割になりました。農学部も、農業を志向する女子が目立ってきたこともあり、増えています。京都は市民が学生を手厚くサポートする。特に女子学生にはみな注目しています。東京にいるのとは全く違う雰囲気を味わえ、親からも独立していけますから、ぜひ来てほしいと思います。
鵜崎: 本校の生徒には男子校の生徒のようなところがあります。チャレンジ精神に溢れ、好奇心も強く、何かやりたいと思っている生徒が多い。人生最大のカルチャーショックは、女子学院に入学したときだったと言う卒業生もいるほど、個性的な生徒が集まっています。京大にお世話になる生徒が一昨年は多かったですが、昨年はそれほど多くなくブームにはなりませんでしたが、特色入試には反応し、今年もその勢いは続いているようです。 いろいろな大学から出張授業などのお話をいただきますが、生徒は学校を介しての情報にはあまり触手を伸ばしません。自分でオープン授業などを見つけて入り込んでいくことに喜びを見出すのが主流のようです。 首都圏の大学に進学する生徒が多い中で、遠方に行きたいという生徒もいますが、保護者がなかなか離したがらないのと、外的な要因で諦めることもあります。口にはあまり出しませんが、小学生で塾に通い、その後6年間、私立の授業料を払ってもらっていますから、親にずいぶん経済的な負担をかけていると考えるのでしょう。 学校としては、生徒が元々持っている興味・関心をできるだけ持ち続けられるように指導しています。生徒は目標を決めるとそれに向かってまっしぐらになり、それらを一つずつ削ぎ落としていきます。しかし将来、それらがどういう形で役に立つかはわかりません。ただ、柳沢先生のところと同じで、あまりこちらが言うと乗ってきませんから、言い方には十分注意しています。

山極: 生徒が選んでくるのは先生ですか、学問のタイトルですか。
崎: 学問のタイトルに先にピンときて、そこから研究内容や先生に関心を持つようです。
山極: 両方必要だと思いますが、これからの学問は、教える側と学ぶ側が一対一になることが大事ですから、先生がすごく重要になってくると思います。そこで附置研でおもろい研究をしている先生たちに発表してもらって高校生との対話の機会を設けたり(京都大学附置研究所・センターシンポジウム「京都からの提言」)、変人を自称する先生の研究に芸人がツッコむ「京都大学変人講座」というのをやっています。一方で、この先生の下で学びたいという気持ちを抱かせるような人をどんどん作らないといけないとも思っています。東京でもやれば高校生は来てくれるでしょうか。
鶴崎: 見つけたら「私が」と。でもみんなで一緒に行こうとは思わない。自分だけが知っていることに心地よさを感じているところがありますから。
齋藤: 本校には小学校でリーダー的な存在だった子と、全くそういうこととは無関係だった子が入ってきますが、前者の中には、全員がリーダーになる必要はないとわかり、自分でそれまで意識してこなかったような能力に気づく子も出てきます。それはそれで悪いことではありませんが、最近少し気になるのは、「輝けない」と不満を漏らす生徒がいること。成績もピカピカで何をやっても目立って、親子ともにみんなからすごいねって思われないからつまらないのだという意味のようです。もちろん6年間の間には、積極的にやろうという子と、そうでない子とは出てきます。全員に自己肯定感を持ってもらえるよう努力しているのですが。 文化祭、体育大会は、本校でも立候補した実行委員が運営していきます。女性教員が多いので、いきおい細かくなりすぎたり、母親になりすぎたりしてしまうきらいもあります。教員が乗りこえるべき壁になることは必要ですが、生徒の自由な発想を妨げてはいけないと、自分たちでも注意しています。 母親の影響は、男の子ほどは強くないと思います。同性である分批判的で、「あの人の言うことは気にしないでください」のような言い方をする生徒もいますが、それはそれで正しい成長かなと思っています。 大学で地方に行く場合、東京にいるとほとんどの学問が地元の大学にありますから、保護者を説得する必要があります。その際の切り札は「医学部に行くから」が多い。親御さんが少しずつ子離れをしていくにはそれなりの理由も必要です。「この大学のこの先生の下で学びたい」などというのもいいと思います。保護者を説得するのも子どもの成長につながるかなとも思っています。そこで親が立ちはだかってはいけませんとお伝えしますが、子どもに「どこでもいい」と言いながら、親の希望を叶えるよう求める例もあります。 女子生徒には男子生徒とは違う力をつけてほしいと思います。女子校にいる間は、「女のくせに」も「女の割に」も言われずに過ごしていますから、大学や社会でそう言われた時にめげない強さが必要です。また結婚、出産でキャリア上、足踏みをすることは必ずありますから、「後ろに下がったのでは?」と思った時も、足踏みを続けていたらいつか前に出られると考えるしぶとさも必要です。それがないと、どんな仕事も続けていくことはできません。そういう強さとしぶとさを、中高の守られている間に身につけさせてあげたいと思っています。0か100かしか考えられないのが優等生の一番の弱点ですから。

武内: 「吉田カレッジ構想」は京大のキャンバスに世界を持ってくるということだと思いますが、私も、「勉強と行事や部活に頑張った子は自らの進路実現も諦めない」といった伝統的な学校経営の価値観を、「世界の中での日比谷」の視点で捉え直す必要があると考え始めています。SSHや東京グローバル10で、生徒を引率して行ったハーバード・ケネディスクールでは、韓国、中国、インドからの留学生が圧倒的で、日本人は1%程度にすぎません。視野を広げ、世界に人脈を広げた彼らが自国に戻り、仕事に、研究に、行政に携わっていくことを考えると、日本の将来に強い危機感を感じます。生徒は生徒で、有名な大学の先生や学生との懇談を通して、将来の目標が明確になり、学習意欲も高まったという者が出る反面、多くは自分の未熟さを意識して、学年が上がるにつれ自己評価が下がっていきます。しかしこれは、次の学びのステップにつながるものでもありますから、今年からはニュージーランドと韓国に姉妹校を作り、短期の交換留学も始めました。異なる価値観を持つ高校生とのつながりの中で、自らの学びについて考え、モチベーションを高めていく。まだまだ解は出ませんが、私自身も挑戦しながら、生徒たちにも挑んでいってほしいと考えています。

座談会へのメッセージ
東京都立西高等学校校長 全国高等学校長協会会長 宮本 久也先生
「世界に通用する大きな器を作る」――生徒が文武二道にチャレンジする中で、主体性を育み、豊かな人間性を涵養することを目指す本校においても、近年は挑戦よりも安全・安定を志向する生徒が目に付きます。大学受験に際しても、保護者の意向に沿ってか、浪人覚悟で挑戦する生徒の割合が少なくなってきています。もちろんこれは、大学院重点化や、就職氷河期以降の就職に強い大学志向などによって、学部段階であえてチャレンジする価値が低下していることによるのかもしれません。ただ教師から見て、18歳段階でのチャレンジを先へ延ばすことは、いずれどこかでそれに迫られることを考えると決して好ましいことではありません。またそれが、「頑張らなくてもいい」というような風潮につながらないかとも懸念しています。
インターネットの普及で、知を授ける場としての高校や大学の役割は低くなってきているのではないかとよく言われます。しかし一方で、「面倒見の良さ」が生徒・保護者の学校選びの一つの指標になっているように、教えられること、正解を与えられることに慣れた子どもたちにとって、その役割は逆に高まっているとも言えます。また核家族化や地縁血縁の希薄化などを背景に、学校には、様々な個性の集まる場の持つ教育力も期待されるようになりました。このことは、学問を教えることを通じて人間を作る、若者を大人にしていく場でもある大学についても言えるでしょう。特に、対話を根幹とする教育で優れた学生を育てようという京都大学のような大学には、それが強く期待されていると思います。
大学入試制度改革にはこれまで、「高大接続システム改革会議」を中心に関わってきましたが、関心が各大学の個別試験へと移る中、各大学それぞれの学部が、どのように対応してくれるのか、その教育改革とあわせて見届けていきたいと思います。また過去5回参加した本座談会については、その中から首都圏公立進学校交流会が生まれ、今はその輪が7校に拡大、校長のみならず教員・生徒の交流も始まるなど、都県を超えた公立高等学校の連携のきっかけともなったことを付記しておきます。








