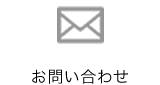教育ジャーナリスト 小林 哲夫さん
小林 哲夫さん
~Profile~
1960年神奈川県生まれ。教育ジャーナリスト。朝日新聞出版「大学ランキング」編集者(1994~)。
近著に『日本の「学歴」』(朝日新聞出版 橘木俊詔氏との共著)。
それでも大学ミスコンは続いている。
昨年11月、東京大駒場祭でミス&ミスターコンテストのイベントが行われた。キャンパスに設営された舞台では、ファイナリストと呼ばれるミス、ミスター候補者、男女あわせて10人が歌、踊り、芸などを披露していた。
観客層はまちまちだ。ファイナリストの家族、大学のクラスやサークル仲間、芸能関係 、特定のファンやマニアなど。ファイナリストの名前を記した鉢巻きをして、熱心にペンライトやうちわを振る人たちもいた。AKB48やジャニーズへの応援を彷彿とさせる。
この日のミスコンイベントでは何も起こらなかった。数年前、駒場祭で「ミスコン粉砕」を訴える学生がデモをしたり、ビラを撒いたりしていたが、そんな光景も見られなかった。
2010年代前半まで、大学ミスコンはそれなりに隆盛を誇っていた。しかし、2010年代半ばから大学ミスコンのあり方が問われ、上智大、東京女子大などは、性の多様化、ルッキズム批判に応えて、外見よりも中身を評価するコンテストに変えている。
2024年はどうだろうか。
ミスコンを開催した大学は次のとおり(判明分)。
東北学院大、筑波大、埼玉大、千葉大、東京大、東京都立大、青山学院大、亜細亜大、桜美林大、大妻女子大、学習院大、学習院女子大、慶應義塾大、国学院大、実践女子大、芝浦工業大、成蹊大、成城大、清泉女子大、中央大、日本大、武蔵大、明治学院大、明治薬科大、明星大、立教大、立正大、横浜国立大、関東学院大、新潟大、静岡大、愛知大、同志社大、立命館大、龍谷大、関西大、関西学院大、松山大、福岡大、佐賀大、長崎大
このうち、大学祭でミスコンのイベントは行われなかったのが、青山学院大、学習院大、 慶應義塾大、成蹊大、成城大、立教大、同志社大、立命館大、龍谷大、関西大、関西学院大などである。これは大学祭実行委員会が開催を認めなかったこと、つまり、大学お墨付きでないことを意味する。
青山学院大のミスコン主催者は、2020年まで大学公認サークルの青山学院大学学友会広告研究会だったが、21年から大学とは無関係の「学生有志」に変わった。現在、同大学のミスコン主催者はこう宣言している。「主催団体ミスミスター青山コンテスト実行委員会は青山学院大学とは一切関係ないものになります」(主催者のX)。
学生が大学の名を勝手に使って協賛企業を集めてやっている、というわけだ。
大学とミスコンは親和性がきわめて低い。2019年、慶應義塾大はこんな告知を出した。
「ミス慶応」等を標榜するコンテストについて
近年、学外において、「ミス慶応」あるいはそれに類する名称を掲げたコンテストが開催されていますが、それらを運営する団体は本学の公認学生団体ではなく、コンテスト自体も慶應義塾とは一切関わりがありません。しかしながら、それらのコンテストには本学の学生も参加しており、一部報道に見られるようなトラブルも発生しています。本学はこうした事態を深く憂慮しており、状況によって今後の対応を検討していきたいと考えます。
塾生諸君へ
この件に限らず、塾生諸君には、さまざまなトラブルに巻き込まれることのないよう十分に注意するよう望みます。何か困ったことがあれば、所属キャンパス学生生活担当窓口に遠慮なく相談してください。(2019年9月30日)
大学の多くはミスコンを快く思っていない。やめてほしい、というのがホンネだ。昨今、大学は教育目標にダイバーシティ(多様化)を掲げている。これは性の多様化も含まれ、外見で評価されるミスコンとは相反するからだ。
法政大は田中優子総長時代、こんな声明を出した。
「『ミスコン』とは人格を切り離したところで、都合よく規定された『女性像』に基づき、女性の評価を行うものである。これは極めて先見性に富む見解であり、本学学生が主体的にこれを提示し、『ミスコン』の開催を認めない姿勢を貫いてきたことは本学の誇るべき伝統と言えるのではないでしょうか。上記に鑑み、いかなる主催団体においても『ミス/ミスターコンテスト』等のイベントについては、本学施設を利用しての開催は一切容認されないものであることをご承知おきください」(2019年11月29日)。
2020年前半以降、新型コロナウイルス感染拡大で、大学ミスコンはYouTubeやインスタグラムなどSNSでの配信がメインとなった。 そしてネットでの人気投票システムができあがり、一部の大学では投票時に課金がなされている。ここでは特定のファイナリストに数十万円をつぎ込んで、その大学のグランプリにさせる動きも見られた。AKB総選挙と同じ構造だ。好きな女子学生を応援する金持ちのミスコンおじさんは、大学ミスコン業界では「石油王」と呼ばれており、キャンパスに歪んだビジネスが持ち込まれている、と言えよう。
こんな状況にもかかわらず、大学でミスコン開催の是非をめぐる論争もあまり起こらないのは、少々さびしい。昨年、京都大でミスコン開催の動きに対する、一部学生の反対運動があった程度だ。
それでも大学ミスコンは続いている。ミスコンに出たい学生、ミスコンでキャンパスを盛り上げたい学生がいるからだ。しかし、きわめて内輪感の強いイベントであり、多くの学生に周知されていない。お金をめぐるさまざまな問題も抱えており、このままではミスコンに関わる学生たちは嫌気がさしてしま い、やがて廃れていくのではないか。そう見ることもできる。
大学ミスコンは、大学の今や将来、そして大学がかかえる問題点をいくつも示してくれる。東京大、青山学院大、慶應義塾大、中央大はOKで、京都大、上智大、早稲田大、法政大はNG――という状況から大学の理念や方針、学生の気質が見えてくる。同レベルの難関校、同じミッション系でも温度差が見られる。また、なぜミス東京大があって、ミスハーバード大がないのか。グローバルな視点から文化の差異、とりわけジャンダー平等の意識差がうきぼりにされ、おもしろい。