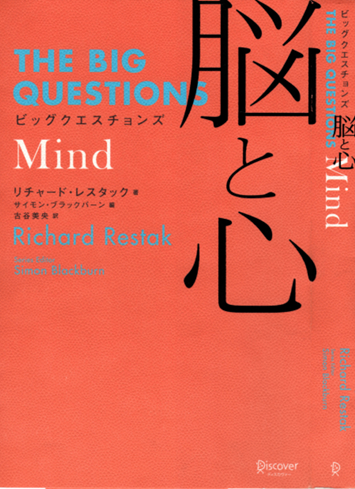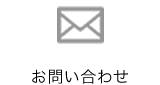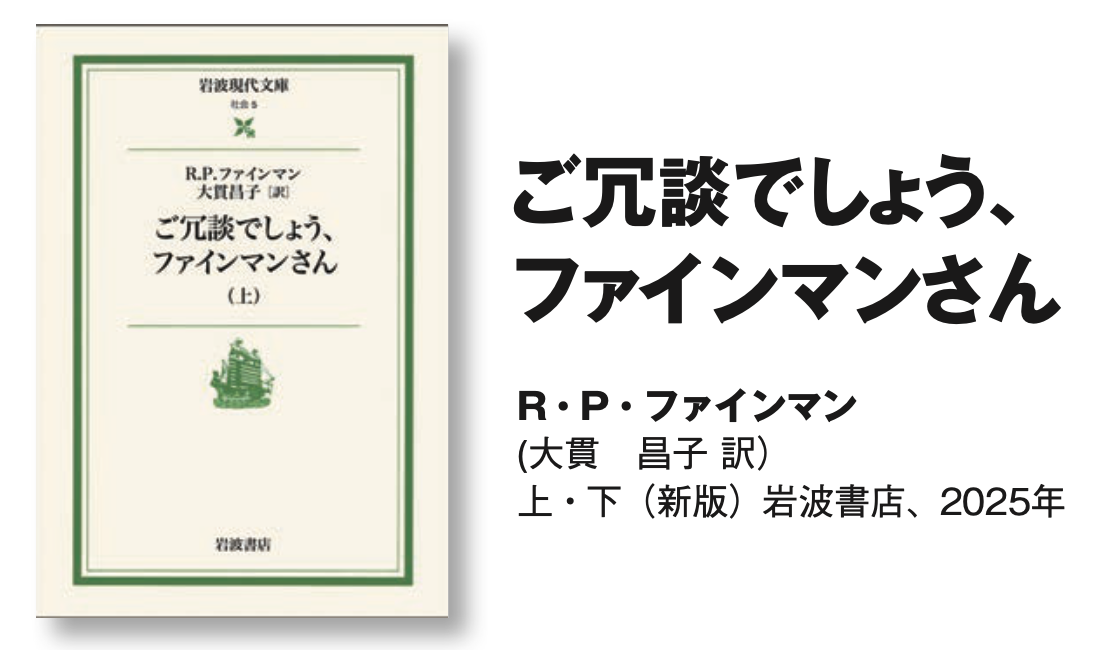
雑賀 恵子さん
Profile
文筆家。京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。著書に『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食について』(人文書院)、『快楽の効用』(ちくま新書)がある。本誌では、2008年11月発行の79号から、ほぼ毎号、書評を寄稿。
冗談やってるファインマンさん、って誰でしょう?
一言で語るなら、物理学者。『ファインマン物理学』は、カリフォルニア工科大学で学部1、2年生を対象に行った講義内容をもとにした物理学の教科書で、世界的に中で有名である。量子電磁力学の発展に大きく寄与したとして、1965年には、朝永振一郎らと共にノーベル物理学賞を共同受賞している。数々の業績は、多方面にわたり影響を及ぼすとともに、将来の技術革新につながる発想もを生み出した。1981年には、「物理学と計算」会議に登壇、量子力学の原理に従うコンピューターの必要性を論じた。スーパーコンピューターの何万倍もの速度を実現する量子コンピューターの開発は、このファインマンのアイディアが端緒になったという。
1918年に米国で生まれ、マサチューセッツ工科大学(あの名だたるMITだ)卒業後、プリンストン大学に進んで博士号を取り、ロスアラモス国立研究所を経て、コーネル大学やカリフォルニア工科大学で教授を務め、1988年に69歳で癌により亡くなる直前まで、生涯現役で活躍し続けた。
そんな恵まれた天才物理学者が、少年時代から始まって学生生活、そしてその後の研究生活までをエッセイにまとめたエッセイ、自叙伝が本書である。経歴だけ書くと、難解な分野における天才が語るエリート人生を思い浮かべてしまうかもしれない。それはそうであるにしても、茶目っ気たっぷり、いたずら大好き、自由気ままで破天荒、そんな生き方が、愉快なエピソードたっぷりに軽妙な筆致で描かれている。
「ご冗談でしょう」というのは、プリンストン大学院入学直後、大学院長主催のお茶会で社交上のヘマをして、院長夫人にいなされた言葉。そんな社交上のヘマに加えて、他にもあちらこちらでヘマをやらかしながらも、いろいろなことに好奇心を抱き、首を突っ込み、手を出し、いたずらっ子が遊んでいるように、学生時代も研究者人生も転がしている。楽しそうだ。何に対しても先入観を持たず、興味を持ち、自分に自信を持って人がしないこともやってみる、そこから創意工夫が生まれる、思わぬ発想も湧き出る。そうした闊達な精神が、リチャード・P・ファインマンを世界のファインマンにしたのかもしれない。そして若い読者は、社会に出ることを勇気づけられるだろう。
だが。ロスアラモス国立研究所、それは原爆開発のマンハッタン計画を遂行したところであり、もちろん彼自身、原爆製造に携わっている。このロスアラモス時代も、楽しかったといきいき語る。原爆実験が成功した時には、考えることを忘れて喜びに溢れかえる。自分が今生きている世の中に責任を持つ必要はない、とフォン・ノイマン(マンハッタン計画に加わっていた天才数学者)に吹き込まれたとうそぶき、「社会的無責任感」を強く持つようになり、物理学そのものに関心をあてて自分を貫く。いつもそういう生き方をしてきたから、楽しい人生を送ってきたし、幸せな男だという。
自分のしていることに没頭し、高い自己評価を持ち、社会とのつながりを考えない。現在のシリコンバレー・エリートたちなどに限らず、そんなひとたちをたやすく思い浮かべることができる。社会的無責任が楽しい人生を送る秘訣であると、もし短絡的に考えているなら、ぞっとする。
ご冗談でしょう、ファインマンさん。