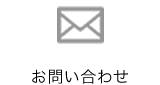Deep Researchの衝撃
新学期が始まりました。高校では他の教科と同時に「総合的な学習の時間」や「課題研究」の授業が始まります。本稿では、AI(人工知能)と探究活動との関わりについて、最近の進展を踏まえて考えてみたいと思います。

秋田県立横手高等学校 教諭 瀬々 将吏さん
Profile
1991年 広島大学理学部物理学科入学、1995年 大阪市立大学大学院理学研究科前期博士課程物理学専攻入学、1997年 同研究科後期博士課程物理学専攻入学、2003年 単位取得退学。博士(理学)。2003年12月 大阪市立大学数学研究所 研究員、2004年12月 京都大学基礎物理学研究所 非常勤研究員/研修員/非常勤講師、2005年10月 慶應義塾大学 研究員、2006年9月 国立台湾大学 研究員、2008年4月 秋田県立横手清陵学院高等学校教諭、2020年4月から現職。兵庫県立芦屋高等学校出身。
探究活動の意義とは
2024年末頃から2025年4月の本稿執筆時までの間に、AI企業各社から「Deep Research」と呼ばれるサービスが相次いで発表されました。このサービスを用いると、従来、生徒が自力で遂行することが難しかった**「先行研究の調査」**が、わずか数分で完了してしまいます。
人間が「○○について調査して」と指示を出すと、AIはこちらの意図を柔軟に汲み取った上で整理されたレポートを完成させます。しかも、そのレポートには原典のリンクが付されているので、AIの解答に誤りがないかどうかをリンクから確認することができます。
より学術的なレベルでは、ElicitやSciSpaceといった研究者向けのツールもあります。これらは研究者が膨大な労力をかけて行う「システマティックレビュー」を代行してくれます。
Deep Research の登場は高校の探究活動に大きなインパクトを与えます。なぜなら、いわゆる「調べ学習」の成果物そのものを代替してしまうからです。レポート課題を提出することだけを目的に Deep Research を使用すれば、それは宿題の答えを丸写しして提出することと同じであり、そこに学びはありません。
一方、Deep Research を含めたAIを「探究のアシスタント」として活用し、学びを深め、テーマ設定を進化させていくような使い方ができれば、素晴らしい成果が得られるでしょう。
大事なのは問う力
このような圧倒的なAIの能力を目の当たりにして、筆者が重要性を痛感しているのが「問う力」です。現在、AIの能力は著しく向上しており、教科学習であれ、探究活動であれ、生徒の疑問に対して普通の学校の教員では太刀打ちできないほど優れた答えを返してくれます。しかも質問できる回数や時間に制限はありませんから、生徒は望む限り対話を深めることができます。
問いをたくさん持っている「問う力」のある生徒はどこまでも賢くなることができ、それがない生徒との間に圧倒的な学力差が生じてしまう恐れも出てきます。AIが知的労働のほぼ全てを代替する世の中では、問題に答えることはあまり重要ではなくなり、「問題(問い)を見出すこと」こそが人間の役割になっていきます。このように言われる状況がすでに現れ始めているのです。
現在の初等・中等教育でも「問う力」は重視されています。例えば、「第4期あきたの教育振興に関する基本計画」でも、最重点課題のひとつが「問いを発する子どもの育成」です。AIの圧倒的な進化によって、その重要性はますます浮き彫りになってきたと言えるでしょう。
問う力を養う探究
では、どうすれば問う力を養えるでしょうか。筆者の答えは「問う力は探究によって養われる」です。
確かに、「問う力」の育成は教科学習の文脈においても重視されてきました。しかし、教科学習の基本的なデザインは、既に確立された学問体系のなかで与えられた問題を解くスキルを身につけることであり、「問う力」はそのスキルを高めるための手段に過ぎません。
一方、「総合的な探究の時間」などのオープンエンドな活動では、「問うこと」そのもの、どれだけよく問題に答えられるかではなく、どれだけ良く問うことができるかが目的になります。
そのためには、高校入試や定期考査に向けて問題を解くトレーニングを積み重ねてきたのと同じように、問いを立てるトレーニングを積み重ねる必要があります。
テーマ設定の難しさ
仮説検証型の探究活動において、活動期間内に解決を目指す問いは「リサーチクエスチョン」と呼ばれます。いわゆる「テーマ設定」とほぼ同義で、探究活動の中でも難しいこととされ、本連載でも何度か話題になっています。
しかし筆者にはその難しさを明確に説明する自信がありませんでした。そこで文献調査のツール「Elicit」を使用して、以下のように問うてみました。
「高校生が科学研究プロジェクトのための実行可能な研究テーマを選ぶ際、それを妨げる主な障壁は何か?」
すると Elicit は、499の関連論文の中から一定の質をクリアした40の論文を選び、その中から200種類のデータを抽出し、5つの障壁を挙げてくれました。
- 生徒の理科・数学の知識不足
- 指導教員、大学教員のサポート、カリキュラム等の不備
- 時間、設備、材料などのリソース不足
- 個人的な障壁(心理的要因)
- 教科学習や受験のプレッシャー
このうち、4. 以外の要因は探究の現場を担当する者からは容易に理解できるものです。高校の環境は大学と異なり、科学研究に全面対応したものではないため、テーマ設定の幅は大幅に狭められたりします。
そこで、これらの制約のもとで探究の質を高めるのに重要なのが、4. の「個人的な障壁」の克服です。
探究活動における「レリバンス」
Elicit によれば、「個人的な障壁」とは、自信のなさ、モチベーションの欠如、研究に対する不安、意思決定の困難さ、興味のなさなどとされます。中でも筆者が探究を指導していて実感するのが、研究テーマに対する興味のなさ、モチベーションの欠如です。
教育現場では、学習単元に対するモチベーションや興味を示す言葉として「興味・関心」という言葉を使いますが、「総合的な探究」では、「自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していく」(学習指導要領)と、生徒の人生にまで踏み込んだ表現がなされています。
つまりは、生徒本人が**「これは自分が解決したい問いだ」もしくは「これは自分の問いだ」と考えているかどうか**ということです。
このような問いに必要なのは、授業で習っていてすごく不思議に感じた、旅行に行って不思議な光景に出会った、本や映画で衝撃を受けた、あるいは実験しているうちに夢中になった、などの学びや体験で、**「自分事だと考えているかどうか」**を左右するのです。
《自分事》のニュアンスが、興味・関心では伝わりにくいということでよく使われるのが「レリバンス(関連性)」という概念です。この概念を使うと、探究活動における良い問いは:
- 自分にとってレリバントな問い
- 社会や学問にとってレリバントな問い
ということになるでしょう。
この「レリバンスの醸成」は高校の探究活動における大きな課題です。レリバントな問いを発する生徒は間違いなく質の高い探究を行えますし、AIに問いかけることで学びを深めていくことができます。
レリバンスについての研究はすでに世界中で蓄積されているようですが、その視点を取り入れた教育方法については、引き続き探究活動の指導を通して蓄積していきたいと考えています。